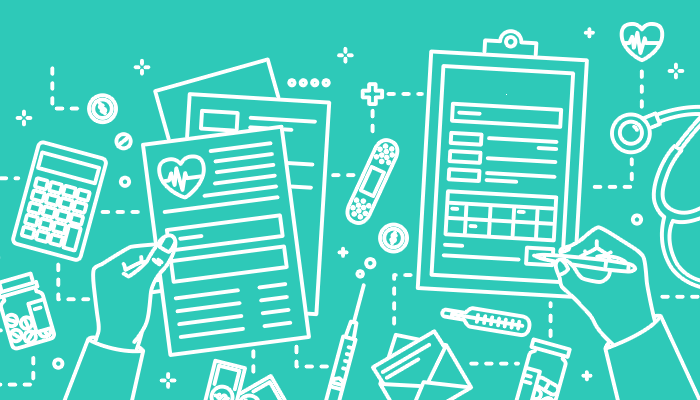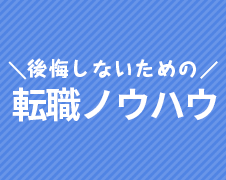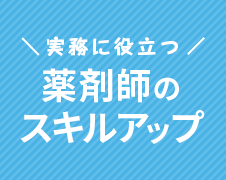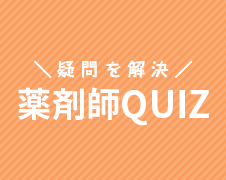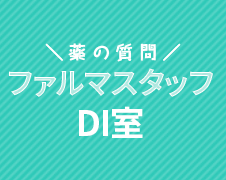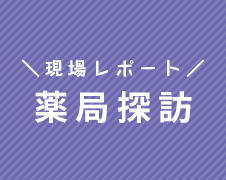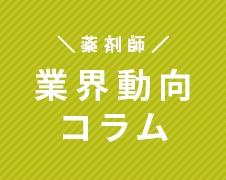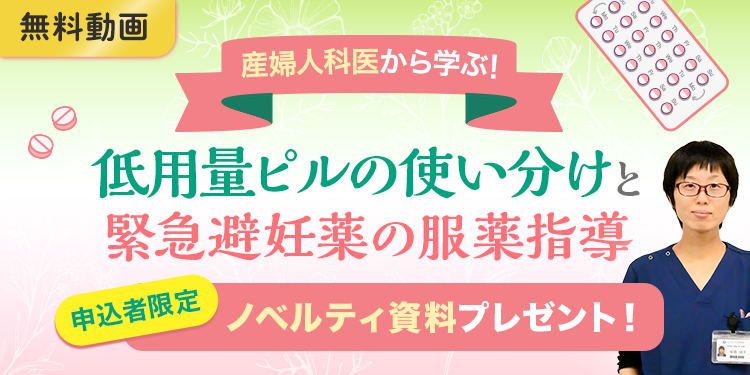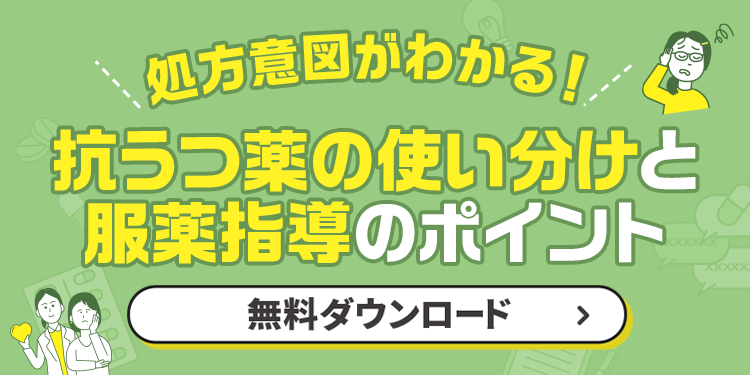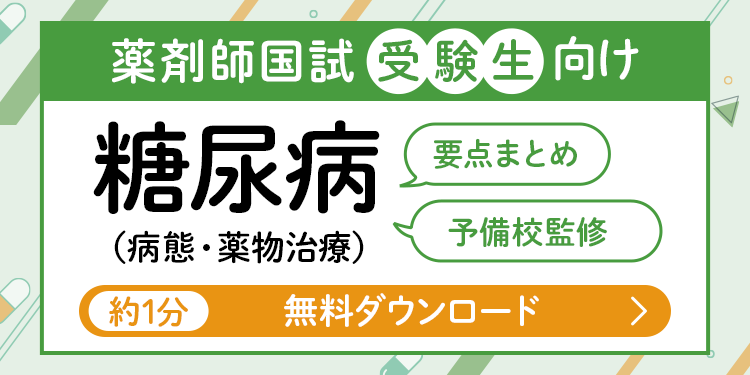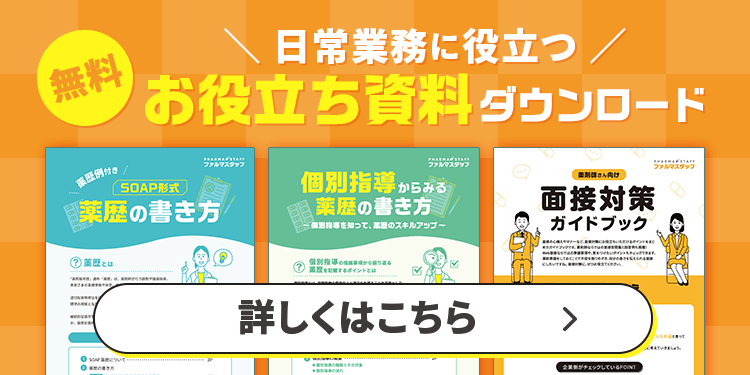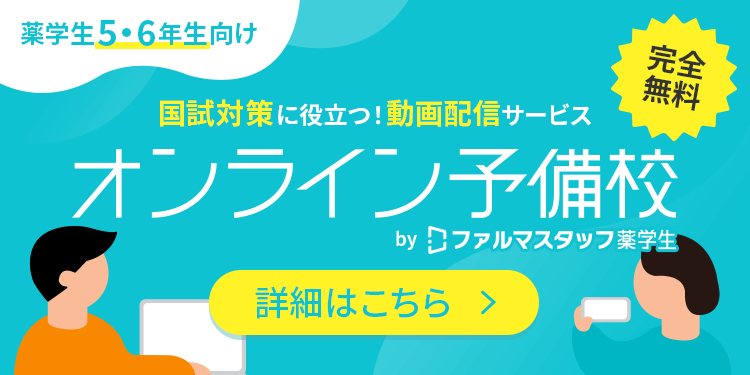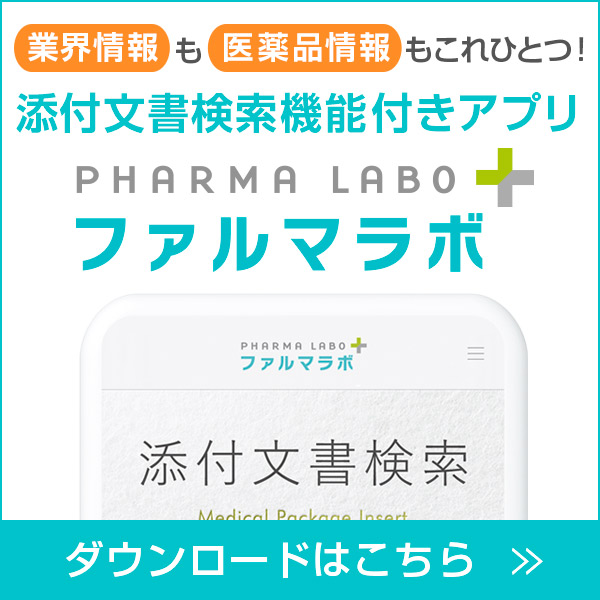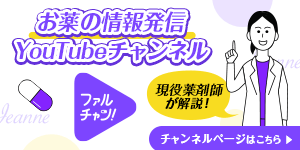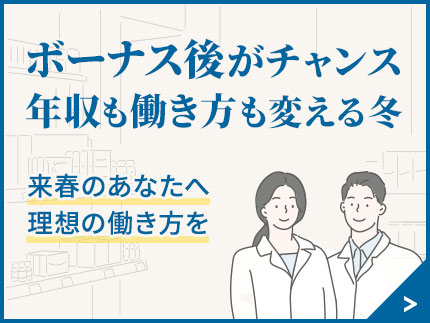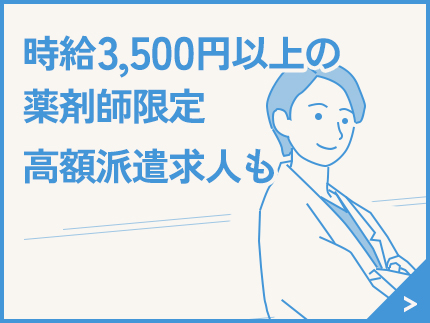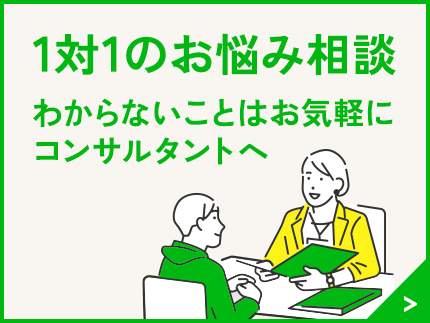クラリス錠
|
Q |
処方目的は? |
|||||||||||||||||||||||||
|
A |
連鎖球菌、グラム陽性菌(ブドウ球菌など)、非定型病原体としてのマイコプラズマやクラミジア、レジオネラに対して強い抗菌作用を示し、肺炎や中耳炎、副鼻腔炎をはじめ多くの疾患に用いられます。また、H.pylori除菌にも用いられ、胃潰瘍・十二指腸潰瘍のみならず、特発性血小板減少性紫斑病やH.pylori感染胃炎など適応も拡大しています。服薬指導時には診療科の確認と共に、受診理由について情報収集しましょう。 抗菌薬の臓器移行性
抗菌薬を選択するにあたっては、適応菌種のみならず、臓器移行性も考慮する必要があります。適応菌種が合致していても、臓器移行性が低ければ治療効果は高まりません。以下のように、抗菌薬の系統によって、臓器移行性が異なります。※ただし、同系統でも薬剤や剤形(内服薬と注射薬など)によっても異なり、文献によって多少の違いがあります。
◎:良好○:中程度△:不良×:不適 |
|
Q |
抗菌以外の作用は? |
||||||||
|
A |
抗菌薬は主に感染症等に用いられますが、マクロライド系抗菌薬は抗菌作用だけではなく、抗炎症作用や免疫調整作用、バイオフィルム(菌膜:この存在により、抗菌薬の感染局所移行性が低くなる)の産生抑制作用、喀痰成分のムチン産生抑制などさまざまな効果が報告されています。また、一般的に抗菌薬はウイルス性の疾患には効果がないと言われますが、免疫調整作用を持つマクロライド系抗菌薬を抗インフルエンザ薬と併用投与することにより、インフルエンザの再感染率上昇を有意に抑制できるという報告や、特にクラリスロ マイシンには、気管上皮細胞における季節性A型インフルエンザウイルスの感染を抑制する効果の報告があります。 マクロライド少量長期投与
びまん性汎細気管支炎や慢性副鼻腔炎、滲出性中耳炎などの慢性感染症に対して、少量のマクロライド系抗菌薬を数ヶ月~数年投与することにより症状の改善をはかる治療法です。主に14員環マクロライドが用いられますが、15員環マクロライドのアジスロマイシン(ジスロマック)でもびまん性汎細気管支炎に同様の効果があると報告があります。これにはマクロライド系の抗菌作用以外の抗炎症作用などが関与していると考えられてい ます。
|
|
Q |
注意すべき副作用は? |
|
A |
重篤な副作用として肝機能障害やQT延長、中毒性表皮壊死融解症や皮膚粘膜眼症候群などが報告されていますので、倦怠感、白目が黄色くなる、動悸、紅斑等の症状が現れた場合はすぐに連絡するよう指導しましょう。/p> |
|
Q |
注意すべき併用薬は? |
|
A |
本剤は、肝代謝酵素チトクロームP450(CYP)3A4阻害作用を有するため、相互作用を生じる可能性のある薬剤が非常に多いです。特にピモジド、エルゴタミン含有製剤、タダラフィル〔アドシルカ〕とは併用禁忌です(同成分のシアリスはアドシルカと用法・用量が異なることから併用注意)。また、天然ケイ酸アルミニウム(アドソルビン)と併用することで、本剤の吸収が低下するとの報告があります。少し時間をあけて服用するように指導する必要があります。他科での併用薬について必ず確認し、相互作用をチェックしましょう。 |
※医薬品情報は掲載日時点の情報となります
あわせて読まれている記事
\登録無料!簡単約1分/
ファルマラボ会員特典
- 薬剤師の業務に役立つ資料や動画が見放題!
- 会員限定セミナーへの参加
- 資料・セミナー・コラムなど最新リリース情報をお知らせ