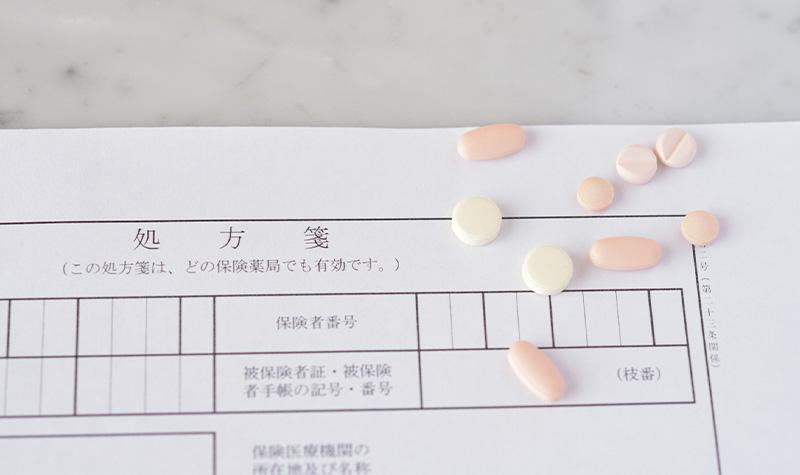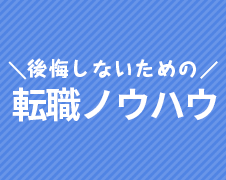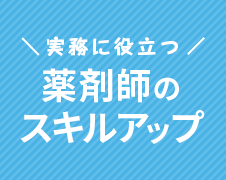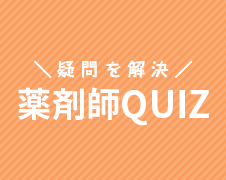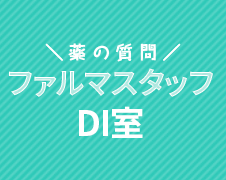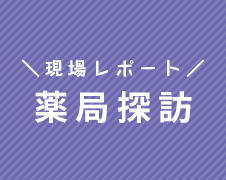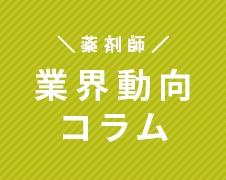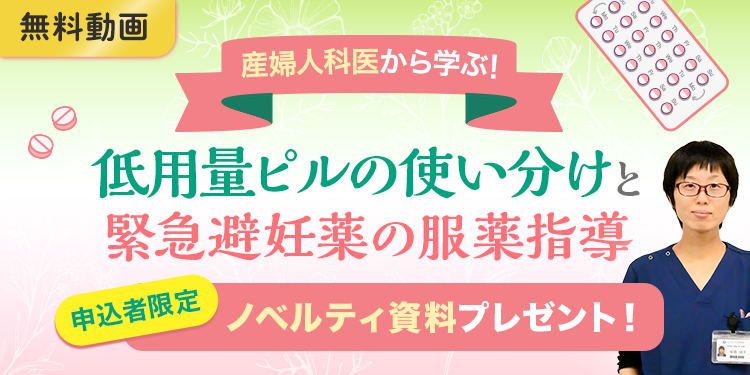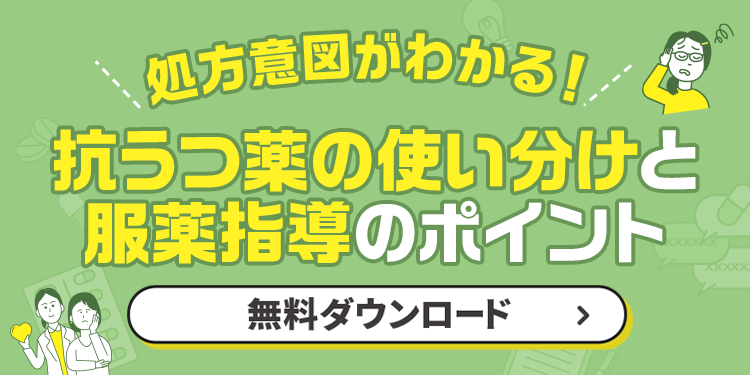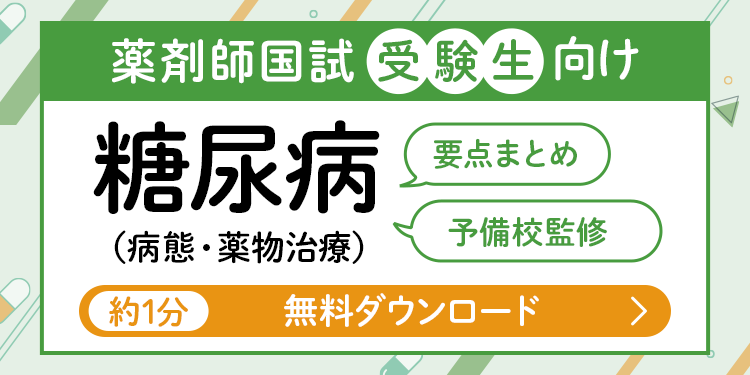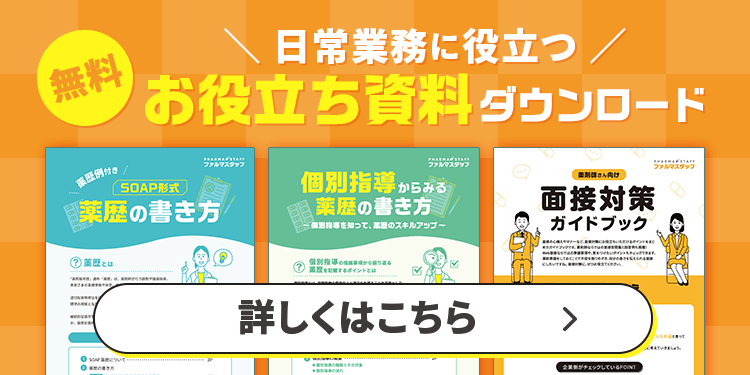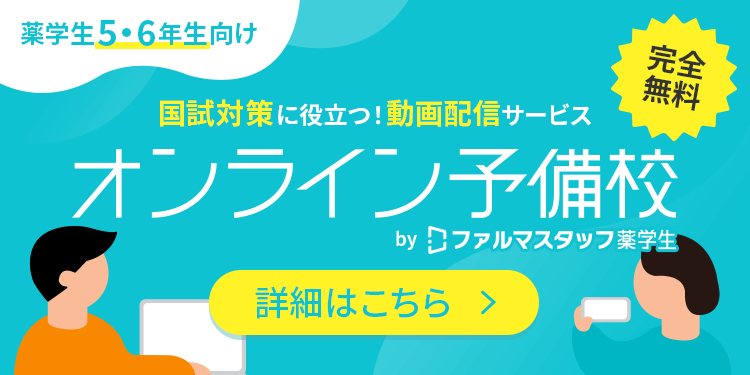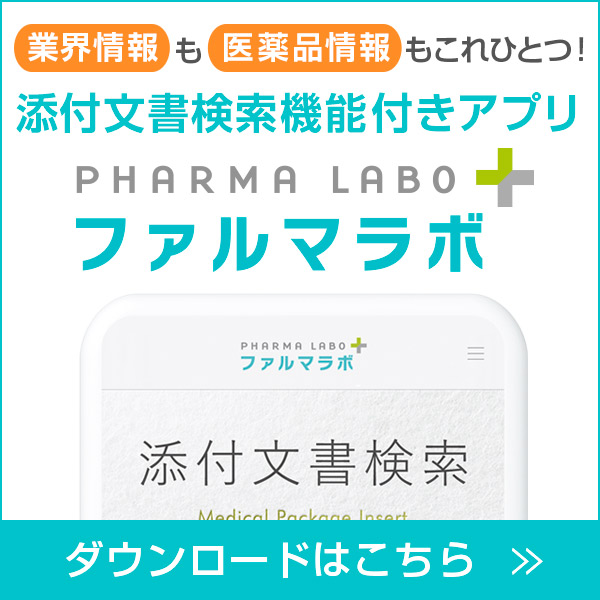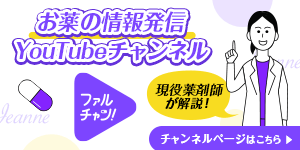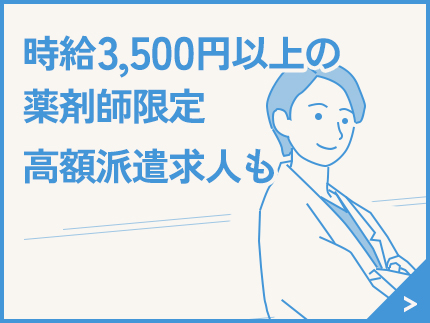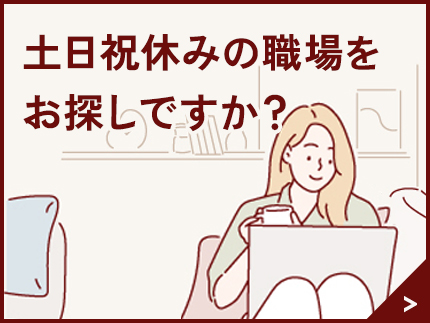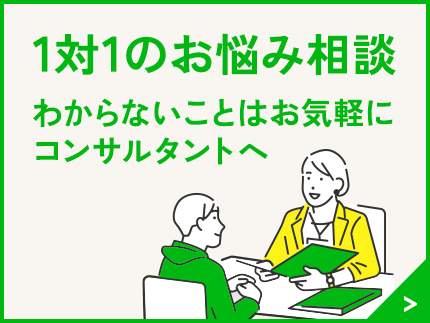- 公開日:2025.05.26
【一覧】吸入ステロイド薬の種類や使い方を薬剤師向けに解説

吸入ステロイド薬は、気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患の治療に欠かせない薬剤です。近年、さまざまな種類の吸入ステロイド薬が開発され、デバイス(吸入器)も多様化しています。
本記事では、薬剤師として知っておくべき吸入ステロイド薬の種類や使い方、患者さまへの指導ポイントについて解説します。
- 吸入ステロイド薬の基本
- 吸入ステロイド薬の種類と特徴について
- デバイス別吸入ステロイド薬の一覧と選び方
- 吸入ステロイド薬の副作用対策と予防法
- 吸入ステロイド薬の服薬指導ポイント
- 吸入ステロイド薬の選択肢を広げて患者さまをサポートしよう
吸入ステロイド薬の基本
気道の炎症を抑制する吸入ステロイド薬は、呼吸器疾患の長期管理薬として広く使用されています。その特徴や作用機序を理解することで、適切な服薬指導や薬剤選択に役立てることができます。
吸入ステロイド薬の作用機序
吸入ステロイド薬は気道に直接作用し、抗炎症作用を発揮します。
その主な作用機序は、気道上皮細胞や肺胞マクロファージだけでなく、T細胞やマスト細胞、血管内皮細胞からのサイトカイン・ケモカイン産生も抑制することです。
さらに、好酸球のアポトーシスを誘導することで、気道への炎症細胞の浸潤や活性化を抑えます。また、血管透過性や粘液分泌の抑制にも寄与し、総合的に気道炎症の鎮静化に働くと考えられています。
経口ステロイド薬との違い
吸入ステロイド薬は経口ステロイド薬と比較して、局所で高濃度に作用する一方で、全身への移行が少ないという特徴があります。
また、一部の吸入ステロイド薬は肺内での活性化(プロドラッグ)や高い脂溶性により、効果の持続性や組織滞留性が向上しています。
吸入ステロイド薬の種類と特徴について

吸入ステロイド薬には、さまざまな種類があり、それぞれ特有の特徴を持っています。
患者さまの症状やライフスタイルに合わせて、適切な薬剤を選択することが大切です。
成分別による分類
以下の表は、代表的な吸入ステロイド薬の成分別分類を示しています。
| 成分名 | 商品名 | 投与頻度 | 適応 | デバイス |
|---|---|---|---|---|
| フルチカゾンプロピオン酸エステル | フルタイド | 1日2回 | 成人・小児 | ディスカス、エアゾール |
| ブデソニド | パルミコート® | 1日1〜2回 | 成人・小児 | タービュヘイラー® |
| シクレソニド | オルベスコ® | 1日1〜2回 | 成人・小児 | インヘラー |
| サルメテロールキシナホ酸塩・ フルチカゾンプロピオン酸エステル |
アドエア | 1日2回 | 成人・小児 | ディスカス、エアゾール |
| ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 | シムビコート® | 1日2回 | 成人 | タービュヘイラー® |
| ビランテロールトリフェニル酢酸塩・ フルチカゾンフランカルボン酸エステル |
レルベア | 1日1回 | 成人・小児 | エリプタ |
フルタイド 添付文書 2024年3月改訂(第2版)
パルミコート 添付文書 2024年1月改訂(第2版)
オルベスコ 添付文書 2020年5月改訂(第1版)
アドエア 添付文書 2020年11月改訂(第2版、再審査結果)
シムビコート 添付文書 2024年1月改訂(第2版)
レルベア 添付文書 2024年6月改訂(第3版、用法及び用量変更)
シムビコートタービュヘイラー
デバイス別吸入ステロイド薬の一覧と選び方

吸入ステロイド薬は大きく4タイプのデバイスで提供されており、患者さまの特性や好みに合わせた選択をすることが重要です。
pMDI(定量噴霧式吸入器)タイプの製品特徴
pMDI(定量噴霧式吸入器)タイプは、薬剤が充填された缶を押すことによって1回分が噴霧される仕組みになっています。
主なデバイス
メリット
デメリット
<スペーサーの活用>
タイミングを合わせるのが難しい小児や高齢者には「スペーサー」と呼ばれる筒状の吸入補助具を併用することで、噴霧された薬剤を一旦留めて自分のタイミングで吸入することができます。
これにより吸入効率の向上と口腔内副作用の軽減が期待できます。
DPI(ドライパウダー吸入器)タイプの特徴
DPI(ドライパウダー吸入器)タイプは、粉末状の薬剤が吸入器に充填されています。
セット時の操作が比較的簡単で、自分のタイミングで息を吸い込んで薬剤を取り込む使いやすさから、一般的に広く使用されています。
主なデバイス
メリット
デメリット
SMI(ソフトミスト定量吸入器)タイプの特徴
SMI(ソフトミスト定量吸入器)タイプは、ボタン操作で薬剤が細かいミスト状に噴霧されます。
吸入ガスを使用せず、微細な粒子が肺に届きやすいのが特徴です。
主なデバイス
メリット
デメリット
ネブライザータイプの特徴
ネブライザータイプは、専用の機械で薬液を霧状にし、マスクやマウスピースを口に加えて吸入します。
薬剤を確実に気管支へ届けられるのが特徴です。
主な種類
メリット
デメリット
デバイス選択において最も重要なのは、患者さまが継続して正しく使用できることです。
患者さまの好みや生活スタイル、理解度も考慮した上で、適切なデバイスを選択しましょう。
-
▼参考資料はコチラ
吸入ステロイド薬の使い分け|J-STAGE
吸入ステロイド薬の副作用対策と予防法
吸入ステロイド薬は経口ステロイド薬と比較して副作用は少ないものの、適切な対策と予防が必要です。
副作用の種類と対応策を理解し、患者さまへの指導に活かしましょう。
局所的な副作用と対応策
吸入ステロイド薬の副作用としては、口腔・咽頭カンジダ症や嗄声(声枯れ)、咽頭刺激による咳嗽などの局所的副作用があります。
とくに嗄声の発生頻度が高いと言われており、その程度によっては日常生活に支障を来す場合もあります。
口腔カンジダ症は、吸入ステロイド薬による局所的な免疫抑制作用によって、カンジダなどの真菌が口腔内や咽頭部で増殖することが主な原因とされています。
一方、嗄声は主にステロイドが声帯筋に影響を及ぼすこと(いわゆるステロイド筋症)が原因とされています。
これらの局所的副作用を予防するためには、吸入ステロイド薬の使用後にうがいを行い、口腔内や咽頭部に残った薬剤をしっかり除去することが重要です。
患者さまには、毎回の吸入後にうがいを徹底するよう指導しましょう。
全身性の副作用とモニタリング
吸入ステロイド薬は、全身性の副作用が出にくい薬剤ですが、高用量を長期にわたって使用する場合では、状況に応じて以下の副作用リスクに留意する必要があります。
高用量を投与した場合に副腎皮質機能抑制のリスクがありますが、現時点では国内で承認された常用量である限り、とくに問題にならないとされています。
長期にわたって高用量を投与する場合には骨密度低下のリスクがあり、カルシウムやビタミンDの摂取を推奨することもあります。
とくに、高齢者や閉経後女性の患者さまで注意が必要です。
その他、小児の成長遅延、白内障、緑内障などの副作用リスクもあるため、高用量を長期にわたって使用する場合は、定期的な副腎機能検査や骨密度測定などのモニタリングが重要です。
吸入ステロイド薬の服薬指導ポイント

吸入ステロイド薬の効果を最大限に引き出すためには、患者さまの理解度と生活習慣に合わせた服薬指導が重要です。
以下に具体的な指導ポイントを示します。
アドヒアランス向上の指導法
吸入ステロイド薬のアドヒアランス向上には以下の指導が有効です。
気道の炎症を抑える重要性と、長期使用の必要性を説明します。
喘息の治療は、吸入ステロイド薬による長期管理を行うことが喘息の発生頻度を抑え、予後改善に有効であることを伝えましょう。なお、吸入ステロイド薬を使用し続けることで、喘息死のリスクを抑制できることが報告されています。
吸入ステロイド薬は、喘息発作や呼吸困難を直ちに改善する薬剤ではありません。抗炎症作用によって、気道の過敏性を改善し、病状を持続的にコントロールする薬剤です。
新規に処方された場合には、効果の実感までに1〜2週間程度かかることを伝えると良いでしょう。
また、「呼吸器の症状がなくても、ステロイド薬の吸入を続けることで発作を予防できる」という理解を促すことも大切です。
吸入アドヒアランスが悪い患者さまには、服薬状況を「見える化」する取り組みが効果的です。
たとえば、記録カレンダーやスマホアプリを用いて吸入回数を可視化し、規則正しい服薬を促します。
また、歯磨きなど日常的な行為や作業と、吸入動作を紐づけることで習慣化を図るアプローチも効果的です。
「朝晩の歯磨きの前に吸入」などの具体的なルーティンを提案しましょう。
症状が改善したからといって自己判断で治療を中断しないよう注意を促します。喘息発作は命の危険にもつながる可能性があることを説明しましょう。
正しい使用方法の指導ポイント
正しい使用方法の指導には以下のポイントが重要です。
各デバイスの説明書を見てもらいながらデバイスの準備(振る、カウンターをセットするなど)の見本を行い、注意事項を説明します。また、使用前に残量確認を毎回行うよう指導しましょう。
実際にデモ器を用いた指導が効果的です。最初に薬剤師が吸入動作を行い、患者さまに練習してもらうと良いでしょう。
とくに初回処方時や、患者さまが高齢者の場合は時間をかけて丁寧に指導しましょう。
ステロイド薬の吸入後は、必ず十分にうがいを行うよう指導します。
うがいが不十分だと口腔カンジダ症や嗄声などの副作用リスクが高まることを説明しましょう。
医師の指示通りの回数と時間帯で使用するよう指導します。
また、吸入ステロイド薬を発作治療薬のように使用しないよう注意を促すことも重要です。
必要に応じてイラストや動画を用いた説明資料を活用し、正しい使用方法を視覚的に理解してもらうのも良いでしょう。
-
▼参考資料はコチラ
吸入指導のポイント 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌|J-STAGE
吸入ステロイド薬の選択肢を広げて患者さまをサポートしよう
吸入ステロイド薬は気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)治療などの呼吸器疾患治療の基本となる重要な薬剤です。その種類やデバイスごとの特性、使用方法を理解することで、患者さまに最適な薬剤選択と指導が可能になります。
薬剤師として、正しい吸入方法の指導や副作用対策、定期的なフォローアップを通じて、長期的な治療継続をサポートしましょう。

監修者:青島 周一(あおしま・しゅういち)さん
2004年城西大学薬学部卒業。保険薬局勤務を経て2012年より医療法人社団徳仁会中野病院(栃木県栃木市)勤務。(特定非営利活動法人アヘッドマップ)共同代表。
主な著書に『OTC医薬品どんなふうに販売したらイイですか?(金芳堂)』『医学論文を読んで活用するための10講義(中外医学社)』『薬の現象学:存在・認識・情動・生活をめぐる薬学との接点(丸善出版)』
あわせて読まれている記事
\登録無料!簡単約1分/
ファルマラボ会員特典
- 薬剤師の業務に役立つ資料や動画が見放題!
- 会員限定セミナーへの参加
- 資料・セミナー・コラムなど最新リリース情報をお知らせ