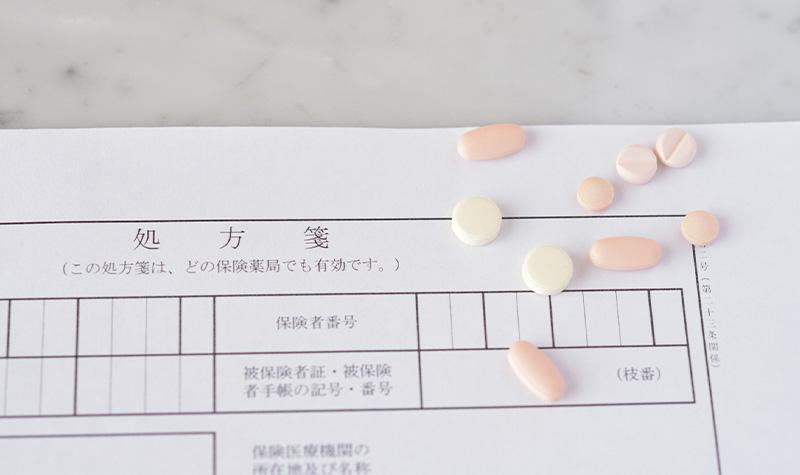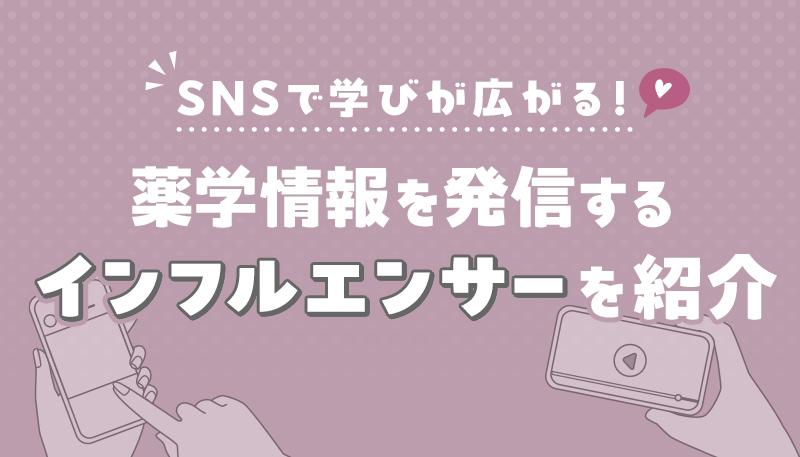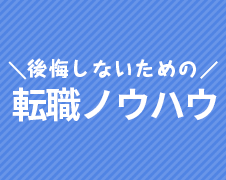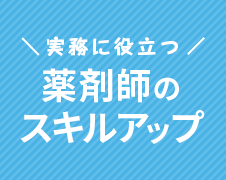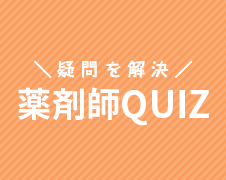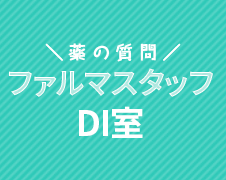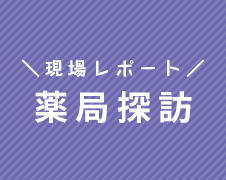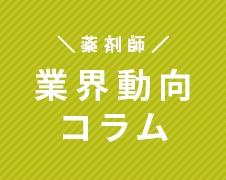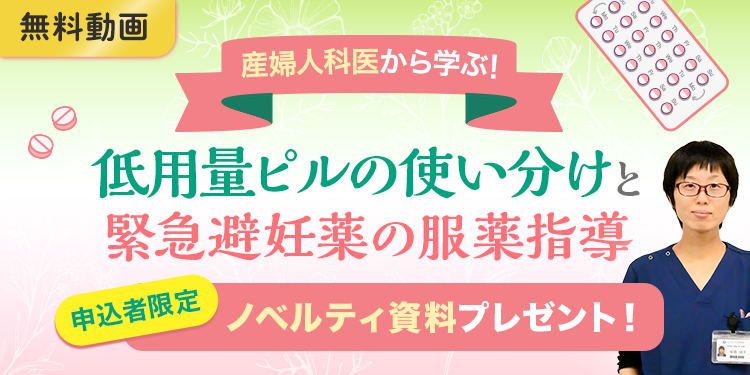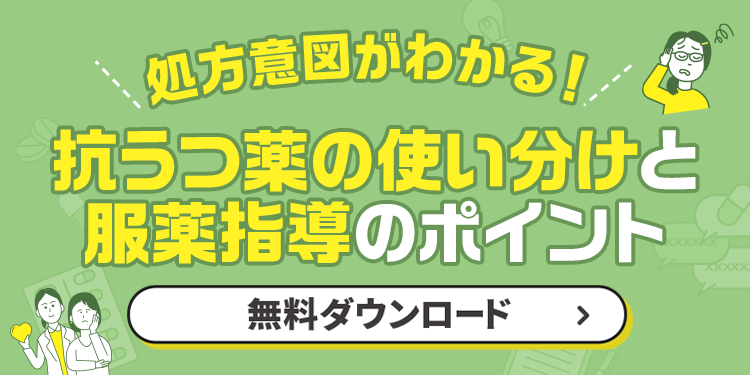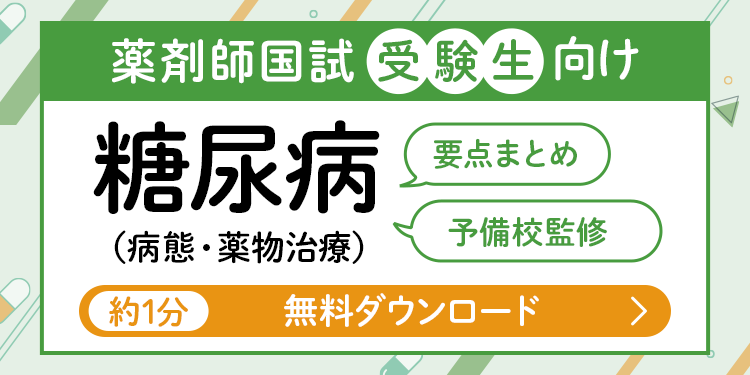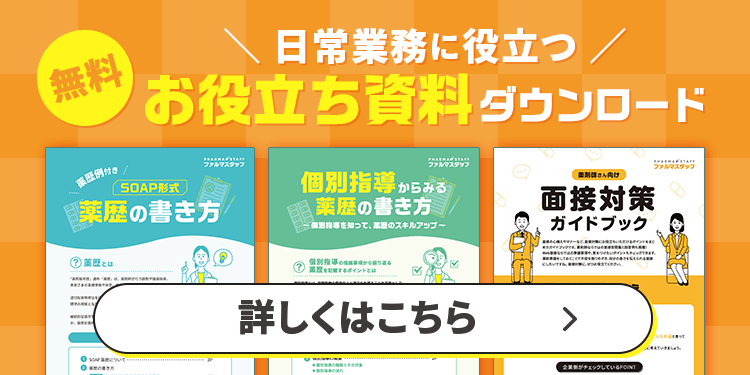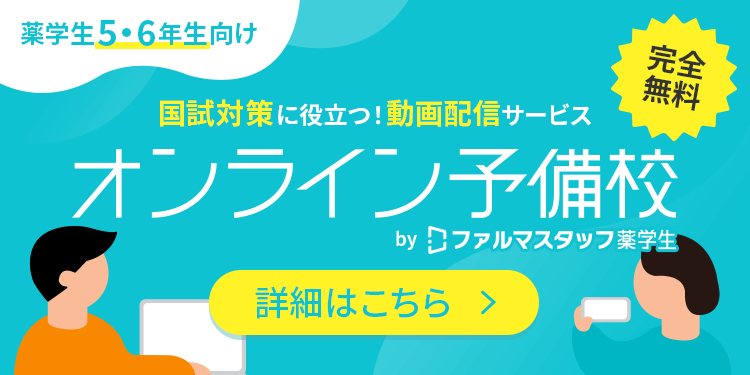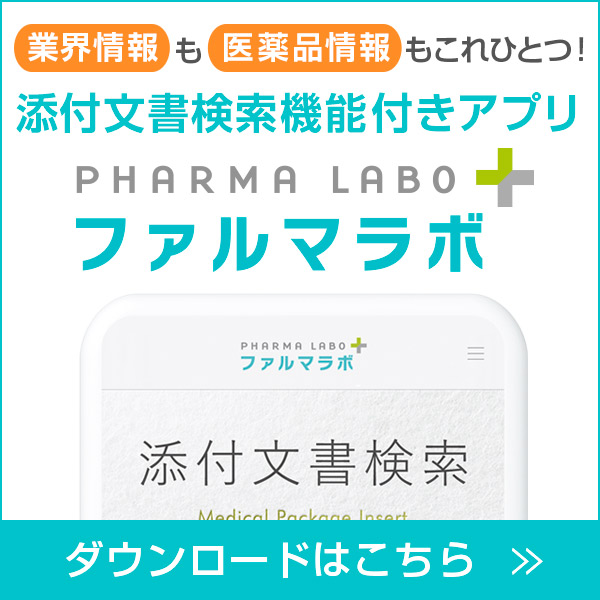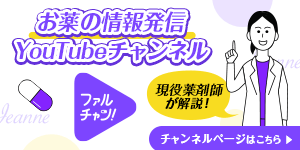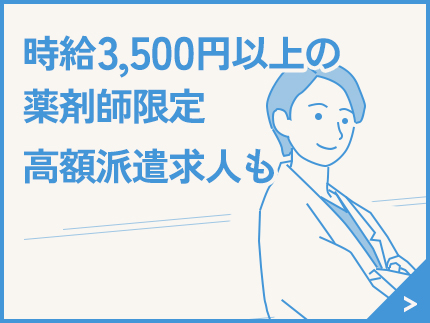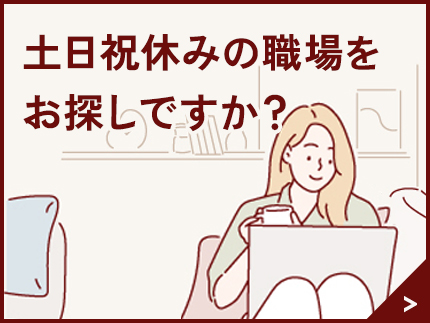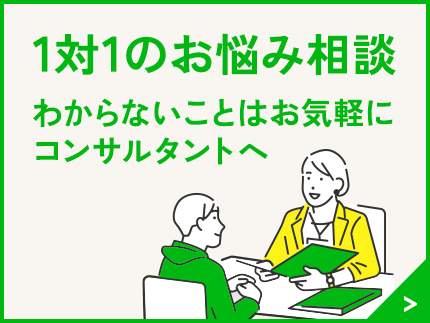- 公開日:2019.07.26
厚生労働省が定める「居宅療養管理指導」とは?利用法や薬剤師の役割を解説

超高齢社会の日本は、在宅医療の重要性が唱えられ、年々需要が高まっています。在宅医療は、介護保険適用の「居宅療養管理指導」、医療保険適用の「在宅患者訪問薬剤管理指導」の2つに分けられるもの。いずれにも関わる機会がある薬剤師だからこそ、これらの違いを説明できるだけでなく、対象者や利用の流れなどをしっかりと把握する必要があるでしょう。
そこでこの記事では、【居宅療養管理指導の対象者や利用の流れなど】を解説していきます。在宅医療に関わるためにも準備しませんか?
「居宅療養管理指導」とは?
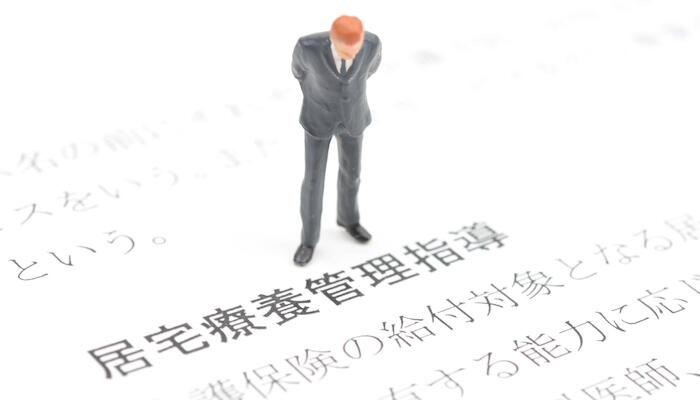
「居宅療養管理指導」について、厚生労働省老健局は下記のように定義しています。
「要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。」
厚生労働省老健局「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成30年1月18日)より引用
介護が必要な患者さまの中には、住み慣れた自宅で過ごしたいと考える方が少なくありません。入院治療、通院治療に次ぐ、第三の選択肢として在宅治療を選ぶ方が増えています。
「自宅で過ごしたい」という意思は尊重すべきもの。だからこそ、医師や看護師などが患者さまのご自宅を訪問し、日常生活を送れるようサポートすることが求められています。
そうした中で、薬剤師の役割は、服薬に関する適切なケアです。処方箋に基づく薬剤管理、服薬に関する相談に応じるほか、体調や副作用の確認や残薬の調整などを行います。
対象者/利用料金/利用可能回数は?

居宅療養管理指導は、どんな方が受けられるサービスなのでしょうか?また、気になる利用料金や利用回数について解説していきます。
対象者について
居宅療養管理指導の対象者は、【要介護1~5の認定を受けている65歳以上の高齢者】です。要支援1~2を受けている方は、「介護予防居宅療養管理指導」が適用されます。
また、65歳未満の方でも利用対象となる場合があります。具体的には、介護保険に加入する40歳~64歳で、初老期の認知症や関節リウマチをはじめ、末期がんなどを含む16種類の特定疾病のいずれかにより要介護認定を受けた方。たとえば、認知機能の低下や歩行困難などを理由に介助を必要とし、「通院および来局が困難な方である」と医師が認めることによってサービスを受けられます。
利用料金について
居宅療養管理指導の利用にかかる費用は、基本報酬額にお薬代を加えた金額となります。他の介護保険サービスと同様に、介護報酬単価の1~3割を負担することで利用できます(居住環境や保険負担割合により金額が異なります)。
基本報酬は3つに区分され、【単一建物居住者1人の場合:507円】、【単一建物居住者2〜9人の場合:376円】、【単一建物居住者10人以上の場合:344円】。さらに麻薬を取り扱えば100円加算されます(いずれも1割負担の場合)。
居宅療養管理指導は介護保険が適用されますが、介護保険の支給限度額の対象ではありません。よって、他のサービスで介護保険を満額利用していても、訪問限度回数の範囲内であれば1割~3割の自己負担で利用することができます。
利用可能回数について
居宅療養管理指導を利用できる回数は、月毎に決まっています。薬剤師からサービスを受ける場合、薬局で働く薬剤師であれば【月4回】、病院や診療所で働く薬剤師であれば【月2回】まで利用が可能です。
また、薬局で働く薬剤師からサービスを受ける際、がん末期または中心静脈栄養を受けている方であれば、【週2回かつ月8回】を限度として利用できます。この時、居宅療養管理指導料を算定する日の間隔は6日以上です。
「居宅療養管理指導」利用の流れ

▼ケアマネジャーへの利用相談
患者さま、またはご家族が、居宅療養管理指導サービスを利用したい旨をケアマネジャーに伝えます。話を受けたケアマネジャーが、患者さまの身体的・精神的な状態からサービスを利用すべきかを判断。「利用したほうがいい」と判断した場合、主治医に連絡がいきます。
▼主治医の判断/ケアプランの作成
主治医が訪問すべきと判断したら、利用頻度や細かなサービスの内容(=ケアプラン)を決めていきます。このように、サービスを受けるには、医師または歯科医師の同意が必要です。また、介護保険を利用するためには、契約書の取り交わしも求められています。
▼<薬剤師の場合>服薬サポート
ケアプランの内容に沿って、医師や看護師などの専門家が患者さまのご自宅を訪問します。薬剤師であれば、医師の指示を受けて、服薬サポートを行うことが多いでしょう。処方箋に基づき調剤したお薬を届けたり、残薬の調整をしたり、衛生用品を販売したりもします。
▼医師や看護師との情報共有
訪問後、医師に患者さまの体調などを報告します。対象の患者さまに関わる看護師やケアマネジャーなど他職種と連携し、必要があればケアプランを変更。次回の訪問に生かします。
薬剤師に求められる役割とは?

上記、『「居宅療養管理指導」利用の流れ』で説明したように、居宅療養管理指導における薬剤師の役割は服薬サポートが中心です。それは、具体的にどのようなことが求められているのでしょうか?代表的な例をご紹介します。
【1】患者さま宅への医薬品の供給
処方箋に基づき、お薬や衛生材料、医療機器の供給や管理を行います。外出が困難な方でも、問題なく治療を受けられるようにサポートをすることが主な役割です。経腸栄養剤や重量のある薬剤などをお届けすることもあります。
【2】患者さまに合わせた調剤
一包化をはじめ、患者さまの服薬状況に合わせた調剤を行います。「指示通りに服薬できない」などの問題を患者さまが抱えていれば、服薬カレンダーを用いた服薬管理や剤型変更(OD錠や顆粒剤など)の提案など、様々な角度から問題解決を目指します。
【3】患者さまへの服薬指導
処方箋に基づき、患者さまがしっかりと薬物治療を受けられるようサポートします。在宅訪問のメリットは、薬の効果や副作用だけでなく、食事・排泄・睡眠などの状況を確認できること。"外来調剤よりも一歩踏み込んだアドバイス"が行えるでしょう。
【4】処方薬変更提案など
患者さまの状態や服薬状況によって、薬の種類や用法・用量などの変更を提案することもあります。また、より患者さまのためになるようケアプランを変更する際、医師やケアマネジャーに情報を共有したり、薬学的見地からアドバイスしたりすることも大切です。
超高齢者社会における重要な役割
【居宅療養管理指導の対象者や利用の流れなど】を解説しました。
居宅療養管理指導の最大のメリットは、自宅にいながら医師や薬剤師などの医療専門家の健康管理や指導を受けられることです。通院が困難な方が日常生活を送れる上で欠かせないサービスと言えるでしょう。
その中で、薬剤師に求められるのは服薬サポートだけでなく、効果や副作用を含めた患者さまの状態チェック。訪問時に得た情報を、医師や看護師などに共有し、患者さまのQOLやADLの向上に取り組むのも大切な役割です。
患者さまが少しでも幸せな療養生活を送ることができるように。居宅療養管理指導の知識やスキルを身につけましょう。
ファルマラボ編集部
「業界ニュース」「薬剤師QUIZ」 「全国の薬局紹介」 「転職成功のノウハウ」「薬剤師あるあるマンガ」「管理栄養士監修レシピ」など多様な情報を発信することで、薬剤師・薬学生を応援しております。ぜひ、定期的にチェックして、情報収集にお役立てください。
あわせて読まれている記事
\登録無料!簡単約1分/
ファルマラボ会員特典
- 薬剤師の業務に役立つ資料や動画が見放題!
- 会員限定セミナーへの参加
- 資料・セミナー・コラムなど最新リリース情報をお知らせ