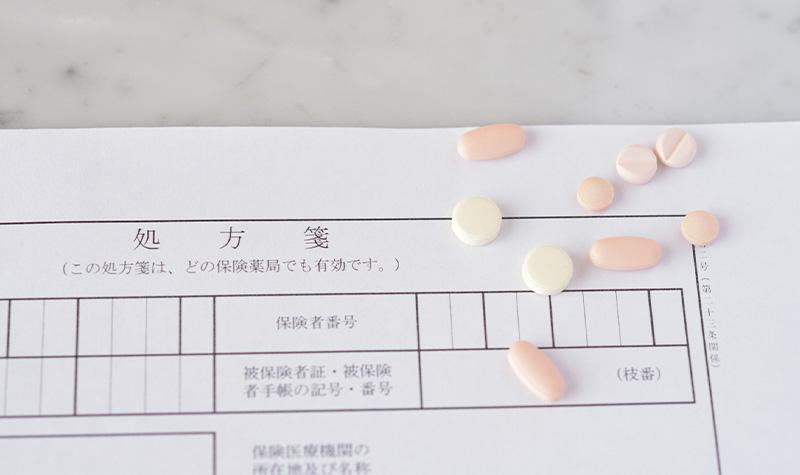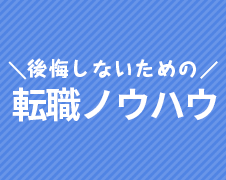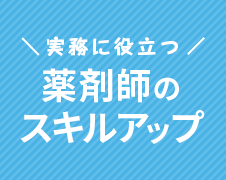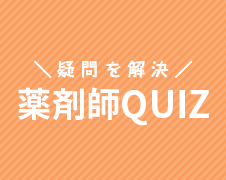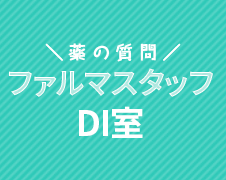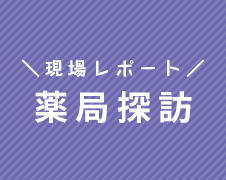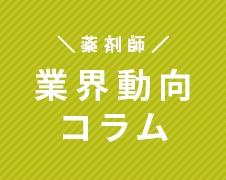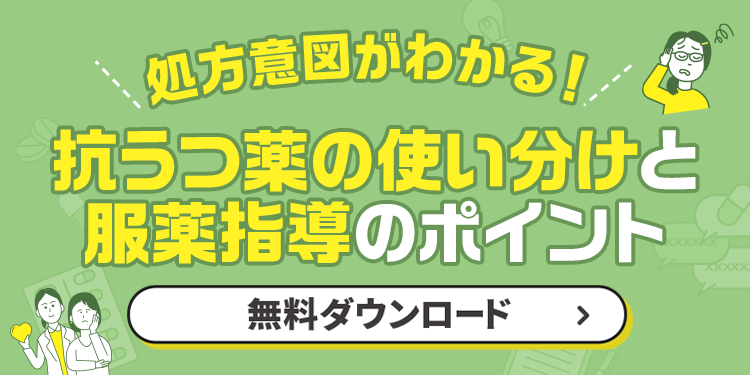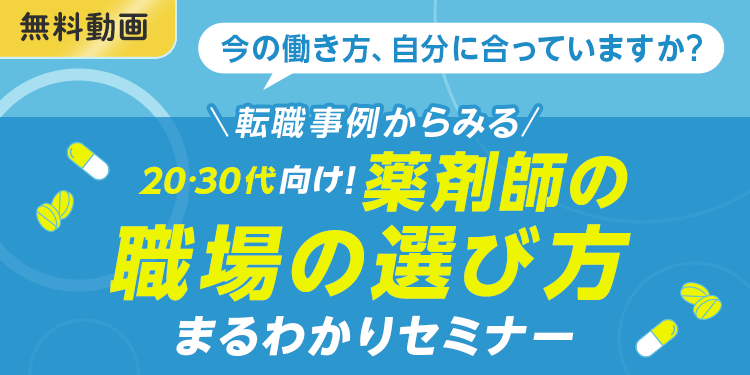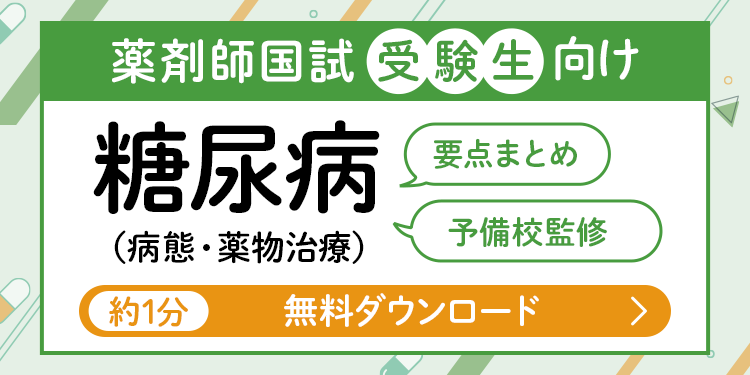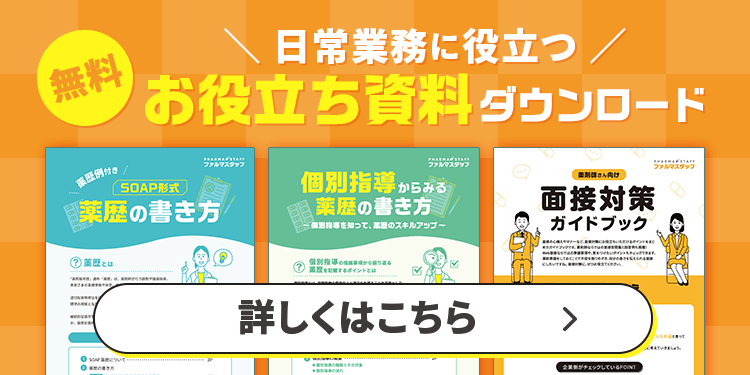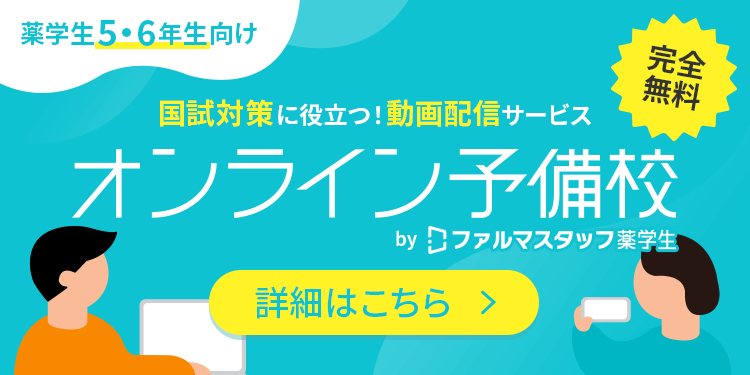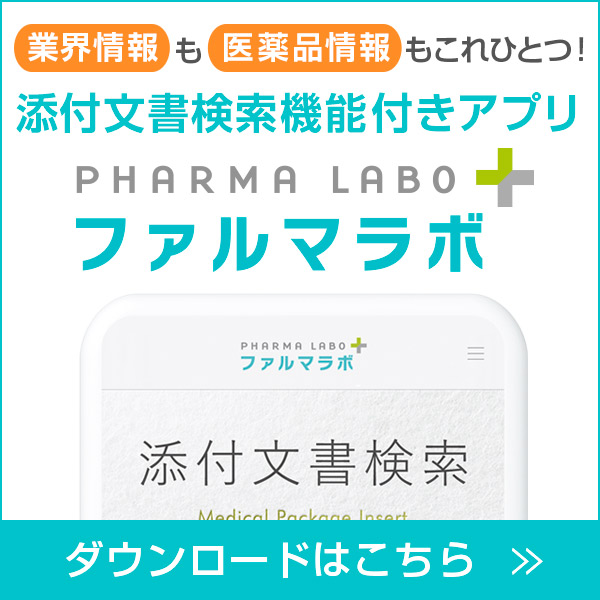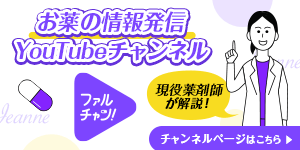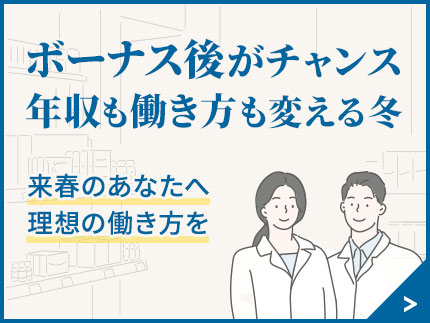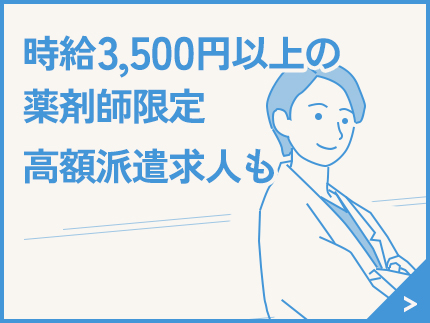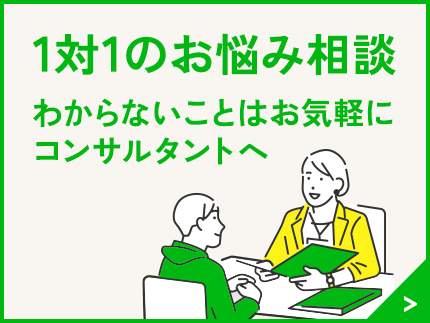- 公開日:2025.06.17
吸入薬指導加算とは?算定要件やレセプトコメントなどを解説

吸入薬指導加算は、薬剤師が喘息や慢性閉塞性肺疾患の患者さまに対して吸入薬の指導を行った際に算定が可能です。
本記事では、2024年度の調剤報酬改定の変更点を含め、吸入薬指導加算の算定要件や点数、レセプト記載方法などについて解説します。
- 吸入薬指導加算の基本
- 吸入薬指導加算の算定条件
- 吸入薬指導加算の算定までの流れ
- 吸入薬指導加算のレセプト請求について
- 吸入薬指導加算と他算定との兼ね合い
- 吸入薬の指導ポイント
- 薬剤師の専門性を評価する吸入薬指導加算
吸入薬指導加算の基本
吸入薬指導加算は薬剤師の専門性を評価する仕組みの一つで、呼吸器疾患をもつ患者さまへの丁寧な指導に対して診療報酬上の評価を受けられる制度です。
呼吸器疾患の治療における薬剤師の貢献を正当に評価する重要な加算といえます。
吸入薬指導加算とは何か
吸入薬指導加算制度は、喘息やCOPDなど、呼吸器疾患の患者さまに対して、薬剤師が吸入薬の適切な使用方法を指導した際に算定できる加算です。
服薬管理指導料やかかりつけ薬剤師指導料に30点を加算できます。
吸入薬は、正しい吸入手技が身についていなければ十分な治療効果が得られません。
デバイスごとに使用方法が異なるため、患者さまには適切な吸入手技の習得が求められます。そのため、こうした専門的な指導の重要性が評価され、調剤報酬の加算対象となっています。
2024年調剤報酬改定のハイライト
2024年調剤報酬改定では、吸入薬指導加算に関する重要な変更が行われました。
従来は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定している患者さまへの吸入薬指導は、かかりつけ業務の一環と考えられ、別途加算できませんでした。
しかし、2024年改定では吸入薬指導の専門性が再評価され、かかりつけ薬剤師指導料を算定した患者さまに対しても条件を満たせば吸入薬指導加算が可能になったのです。
この変更により、かかりつけ薬剤師が担当する患者さまにも、より専門的な吸入薬サポートを提供しやすくなりました。
薬局で実施できる呼吸器疾患の患者さまへのケアがさらに充実したと言えるでしょう。
地域支援体制加算の見直し
2024年調剤報酬改定では、地域支援体制加算についても大きな見直しが行われており、特に加算3・4においては「服薬情報等提供料」の実績が重要な要件となっています。
従来、吸入薬指導加算は服薬情報等提供料と併算定不可のため、実績に含めることができませんでしたが、今回の診療報酬改定から、「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」の中に吸入薬指導加算(文書による情報提供の場合に限る)を含めても良いことになりました。
この変更により、吸入薬の処方が多い薬局では、地域支援体制加算の実績要件を満たしやすくなりました。
また、多職種連携や地域包括ケアの推進がさらに重視され、薬局が医療・介護機関と連携しやすくなる体制が求められています。
-
▼参考資料はコチラ
一般社団法人日本呼吸器学会令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】|厚生労働省
個別改定項目について|厚生労働省
令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について|厚生労働省
吸入薬指導加算の算定条件

吸入薬指導加算の算定条件(対象・頻度・指導内容)について整理します。
対象疾患と患者さま
吸入薬指導加算の適用対象は以下のとおりです。
これらの疾患で吸入薬が処方されている患者さまが対象です。呼吸器疾患の管理において、適切な吸入手技の習得は症状コントロールに直結するため、継続的な指導と確認が重要視されています。
算定間隔
基本的な算定頻度は「3ヶ月に1回まで」と定められていますが、前回の算定時とは別の吸入薬が処方された場合で、必要な吸入指導などを別に行ったときには、3ヶ月以内でも算定可能です。
たとえば、ドライパウダー式の吸入薬を使用していた患者さまに、新たにスプレー式の吸入薬が処方された場合などが該当します。
吸入方法が大きく異なるため、新たな使用方法の指導が必要となります。
指導内容
有効な指導として認められるためには、説明のみではなく実際に以下のような指導資材を用いた実践的な指導が求められます。
また、吸入指導を行うに当たっては、日本アレルギー学会による「アレルギー総合ガイドライン」などの公的ガイドラインを参照することが推奨されています。
吸入薬指導加算の算定までの流れ

吸入薬指導加算を算定するためには、適切な手順を踏む必要があります。
患者さまの同意から医療機関への情報共有まで、実務の流れを解説します。
患者さまの同意取得
算定するためには、以下のケースに該当し、指導実施前に患者さまの同意を得る必要があります。
保険医療機関からの依頼がある場合
医師や医療機関から吸入指導の依頼があった場合、患者さまの同意を得たうえで指導を実施します。
医師の指示があるため比較的スムーズに指導へ移行できるでしょう。
患者さまやご家族からの希望があるなど、吸入指導の必要性が認められ、医師の了解を得た場合
医療機関からの直接依頼がなくても、患者さまやそのご家族からの希望があった場合など、吸入指導の必要性が認められる場合には、医師の了解と患者さまの同意を得たうえで指導を実施します。
必ず医師に相談し、了解を得てから指導を行うようにしましょう。
医療機関への情報提供
患者さまへの指導後は医療機関への情報提供が不可欠です。
これは加算算定の必須条件となっています。
文書による情報共有
吸入指導の内容や患者さまの吸入手技の理解度などについて、保険医療機関へ文書で報告します。
お薬手帳の活用
情報提供手段としてお薬手帳を用いることも認められています。
ただし、吸入指導を行った結果、患者さまの吸入薬の使用について疑義などがある場合には、処方医に対して必要な照会を行うことが求められます。
-
▼参考資料はコチラ
調剤報酬点数表|厚生労働省
調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省
吸入薬指導加算のレセプト請求について
正確なレセプト記載は返戻防止の要です。
吸入薬指導加算特有の記載ルールを理解しておきましょう。レセプト摘要欄には以下の2項目の記載が必須となります。
コード「850100480」を使用して調剤日を記録します。
表示文言:(元号)yy"年"mm"月"dd"日"
コード「830100446」を使用して薬剤名を記載します。
表示文言:******
吸入薬指導加算と他算定との兼ね合い
吸入薬指導加算を算定する際は誤った請求を避けるため、相互関係を理解しておきましょう。
手帳減算時の服薬管理指導料
お薬手帳を持参していない患者さまが多い薬局では、手帳減算の対象となり、この場合は吸入薬指導加算を算定できません。
手帳の活用を促すことが薬局にも求められています。
かかりつけ薬剤師包括管理料
かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している場合は、吸入薬指導加算を別途算定できません。
包括管理料にはすでに各種指導料が含まれているためです。
特別調剤基本料Aを算定する一部の薬局
特別調剤基本料Aを算定する薬局が「特別な関係を有する医療機関」に情報提供した場合は、吸入薬指導加算を算定できません。
特別調剤基本料Bを算定する薬局
特別調剤基本料Bを算定する薬局(特定の医療機関敷地内薬局など)では、そもそも服薬管理指導料等が算定できないため、吸入薬指導加算も算定できません。
服薬情報等提供料
吸入薬指導加算に関する同一内容の情報提供については、服薬情報等提供料を重複して算定できません。
-
▼参考資料はコチラ
調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省
吸入薬の指導ポイント

患者さまの理解を深め、正しい使用法を定着させるために、4つのステップを意識した指導が効果的です。
ステップ1:持ち方の指導
初めて吸入薬を使用する患者さまには、基本的な持ち方から指導しましょう。
たとえば利き手と補助手の役割伝え、「左手でデバイスを持ち、右手でボタンを押しましょう」などと指導します。
ステップ2:吸入器の各部位の役割を説明
患者さまが吸入器を使用しやすくなるよう、各部位の役割を説明します。
ステップ3:操作方法の習得
吸入器の操作の順序とポイントを強調します。
デバイスによって操作方法は異なりますが、一般的に留意すべき事項例は以下の通りです。
ステップ4:正しい吸入手技の習得
吸入手技の習得も重要です。
デバイスに応じた最適な方法を分かりやすく説明していきましょう。
実践的な指導においては、日本喘息学会が公開している吸入指導動画なども積極的に活用するとより効果的です。
視覚的に学べるため、患者さまの理解度が高まります。
-
▼参考資料はコチラ
吸入操作ビデオ|日本喘息学会
薬剤師の専門性を評価する吸入薬指導加算

吸入薬指導加算は、薬剤師による専門的な吸入指導を評価する制度です。
2024年度の調剤報酬改定により、より多くの患者さまに指導が行えるようになりました。
本記事でご紹介した算定要件や指導のポイントを参考に、適切な吸入薬指導と確実な加算算定を実践し、患者さまの治療をしっかりサポートしていきましょう。

監修者:青島 周一(あおしま・しゅういち)さん
2004年城西大学薬学部卒業。保険薬局勤務を経て2012年より医療法人社団徳仁会中野病院(栃木県栃木市)勤務。(特定非営利活動法人アヘッドマップ)共同代表。
主な著書に『OTC医薬品どんなふうに販売したらイイですか?(金芳堂)』『医学論文を読んで活用するための10講義(中外医学社)』『薬の現象学:存在・認識・情動・生活をめぐる薬学との接点(丸善出版)』
あわせて読まれている記事
\登録無料!簡単約1分/
ファルマラボ会員特典
- 薬剤師の業務に役立つ資料や動画が見放題!
- 会員限定セミナーへの参加
- 資料・セミナー・コラムなど最新リリース情報をお知らせ