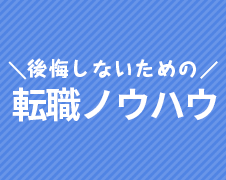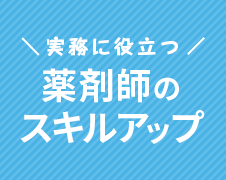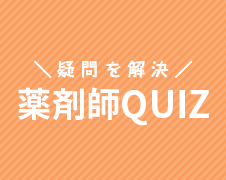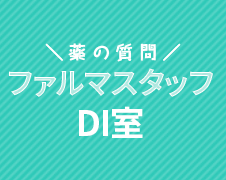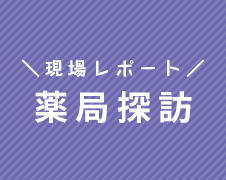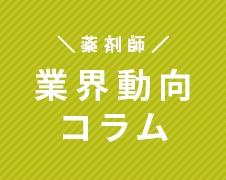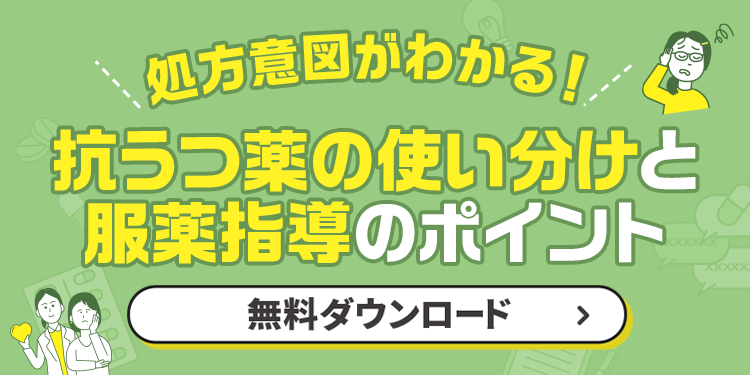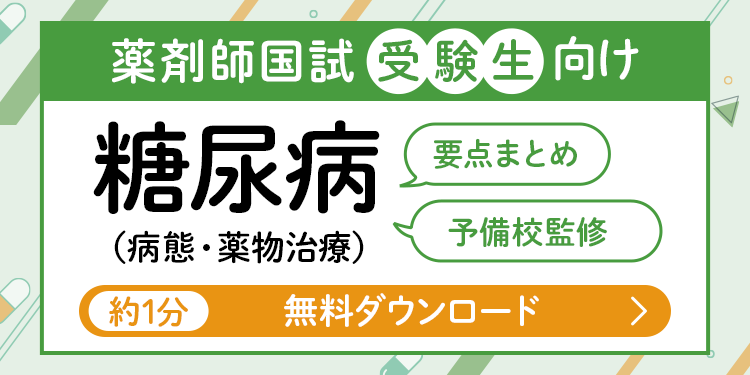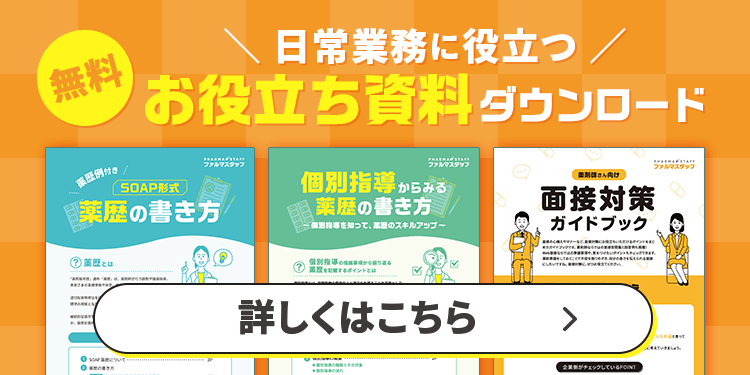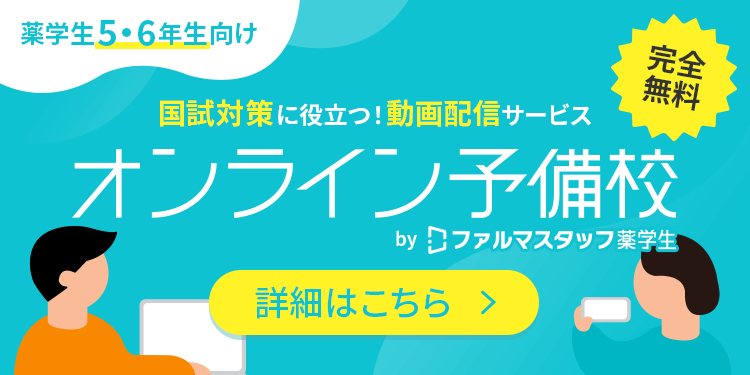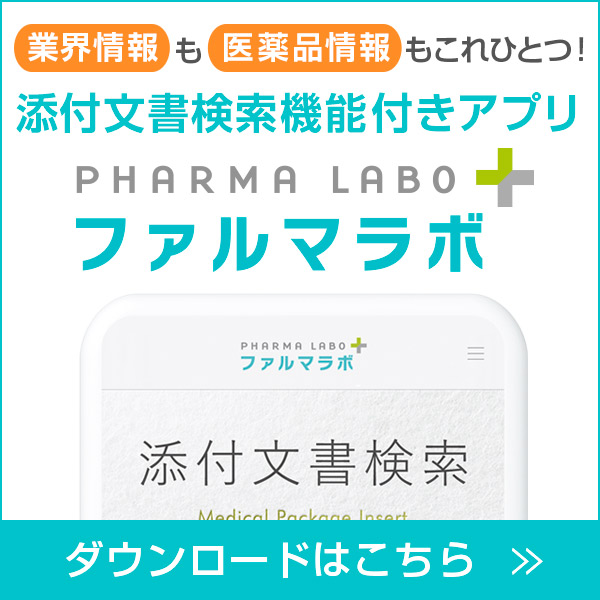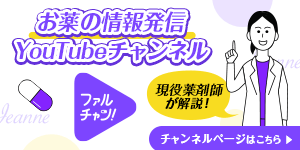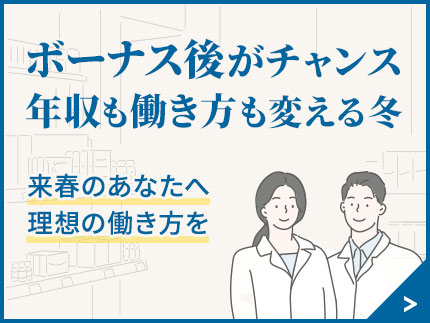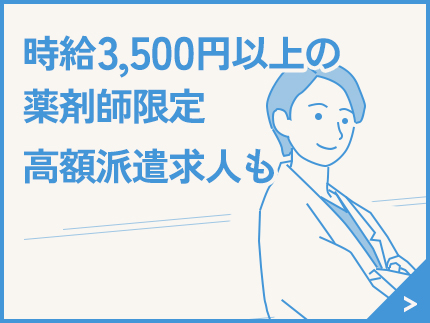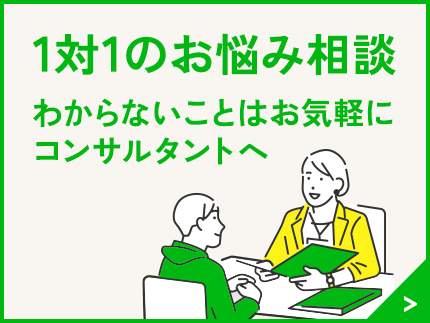- 公開日:2025.06.05
マイナ保険証利用率の最新要件は?医療dx推進体制整備加算など2025年診療報酬改定を解説
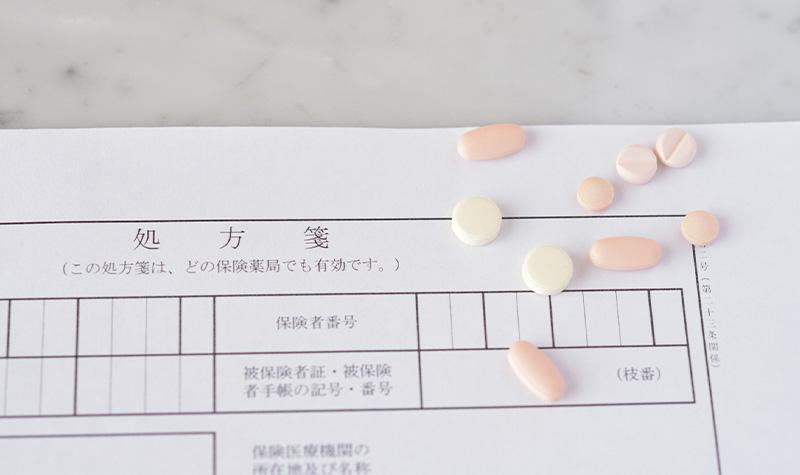
2024年6月の診療報酬改定では、医療DX推進体制整備加算の新設やマイナ保険証利用率の要件が導入されました。
さらに、2025年4月の改定ではこれらの見直しが行われ、薬局経営に大きな影響を与えています。
本記事では、最新のマイナ保険証利用率の要件や医療DX関連加算の改訂内容と対応策を解説します。
- 2024年度診療報酬改定の全体像
- 医療dx推進体制整備加算の見直し
- 特定薬剤管理指導加算3-ロの見直し
- 2025年4月期中改定を受けて薬剤師が注力すべきこと
- 診療報酬改定を踏まえて今後の薬局経営について考えよう
2024年度診療報酬改定の全体像
2024年度の診療報酬改定では、医療現場の質向上と効率化を目指して大幅な見直しが行われました。
ここでは、その全体像や主なポイントに加え、2025年4月施行の改定内容についてもわかりやすく解説します。
2024年6月に施行された診療報酬改定のポイント
改定の主なポイントは以下の通りです。
これらの取り組みにより、医療現場の質と効率のさらなる向上が図られています。
「地域包括ケアシステムの構築」「患者のための薬局ビジョン」「医療DX」の実現に向けた改定
2024年度の診療報酬改定は、高齢化の進展に伴う医療ニーズの変化や、医療従事者の働き方改革、医療DXの推進など様々な課題に対応するために行われました。
薬剤師には地域包括ケアシステムの一員として、多職種と連携しながら患者さまを支える役割が期待されています。また、患者さま中心の薬学管理を実践し、地域住民の健康増進に貢献することも求められています。
改定のスケジュールと準備期間
例年4月に施行される診療報酬改定ですが、2024年度は6月に施行が後ろ倒しとなりました。このスケジュール変更は、現場の混乱を避け、よりスムーズな移行を促すための措置であり、多くの調剤薬局が余裕を持って改定対応を進めることができたと言えます。
診療報酬本体の改定率と調剤報酬への影響
診療報酬本体の改定率は+0.88%となり、そのうち0.28%は40歳未満の勤務者の賃上げに充てられます。
調剤報酬の改定率は+0.16%であり、本体の改定率と比較すると低いものの、薬剤師の業務に影響を与える重要な変更が含まれています。
とくに、医療DXの推進に関する項目は今後の薬局経営において重要な意味を持つでしょう。
具体的には、マイナ保険証や電子処方箋の活用を評価する仕組みが強化されることで、これらのデジタル技術に早期対応した薬局は加算の取得によって収益を確保できます。
一方で、対応が遅れた薬局は今後加算の取得ができなくなるなど、収益面で不利益を被ることも出てくるかもしれません。
2025年4月に施行された診療報酬改定のポイント
こうした背景や現場の状況変化を受けて、2025年4月には期中改訂が実施されました。
この改定では、医療DX推進体制整備加算の見直しや、特定薬剤管理指導加算の評価など、デジタル化や薬局業務の負担増加に対応するための重要な変更が盛り込まれています。
今後の薬局経営を左右するポイントとして、改定内容をしっかり把握し、適切に対応しましょう。
医療DX推進体制整備加算の見直し

医療DX推進体制整備加算は、2024年度の調剤報酬改定の際に新設され、同年10月からは施設基準やマイナ保険証利用率に応じて点数が設定されています。
また、2025年4月から要件や点数が引き上げられることが発表されており、すでに適用されています。
マイナ保険証利用率に応じた段階的な点数設定
2025年4月からは、マイナ保険証利用率の要件と点数が見直され、加算点数が2~3点引き上げられています。
<医療DX推進体制整備加算の点数改定>
| 加算名称 | 点数 | マイナ保険証利用率 |
| 医療DX推進体制整備加算1 | 7点→10点 | 45%以上 |
| 医療DX推進体制整備加算2 | 6点→8点 | 30%以上 |
| 医療DX推進体制整備加算3 | 4点→6点 | 15%以上 |
利用率の算出方法については、原則として「適用月の3カ月前のレセプト件数ベース」のマイナ保険証利用率を用います。
ただし、2024年10月から2025年1月までは、「2カ月前のオンライン資格確認件数ベース」のマイナ保険証利用率も選択可能でした。
さらに、これらに代えて「前月および前々月」のマイナ保険証利用率を用いることも認められており、適用月の3カ月前のレセプト件数ベース、2カ月前のオンライン資格確認件数ベース、または1カ月前のいずれかで、最も高い利用率の月を選択できました。
また、マイナ保険証の利用促進に向けては、例として以下の取り組みが挙げられます。
受付カウンターの見やすい位置に設置し、すべての患者さまに利用を促します。
マイナ保険証の利用メリットや操作方法についてスタッフが説明できるようにします。
利用率を確認し、目標達成に向けた対策を講じます。
電子処方箋に関する要件
加えて、2025年4月からは医療DX推進体制整備加算の要件として、電子処方箋への対応が必須となります。
厚生労働省の資料によると、2025年2月時点で薬局の電子処方箋普及率は67.9%に達しており、医科診療所・歯科診療所と比較して普及が進んでいることから、薬局に関しては経過措置を終了する判断がなされました。
これまでは経過措置として電子処方箋に対応していなくても算定可能でしたが、2025年4月以降はこの経過措置が終了しています。
電子処方箋に関する主な要件は以下の通りです。
電子処方箋管理サービスに接続できる環境を整備する必要があります。
たとえば、HPKIカード(医療機関認証用ICカード)の取得や電子署名機能の実装、オンライン資格確認システムとの連携環境の構築などが挙げられます。
電子処方箋を受け付け、調剤する体制を有するとともに、紙の処方箋を含めて原則としてすべての調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録することが求められます。
電子処方箋導入には大きく分けて3つのメリットがあります。
従来の紙の処方箋では、診察後に患者さまが薬局へ行き、処方箋を提出して調剤を待つ必要がありました。
しかし、電子処方箋では患者さまがマイナポータルで「マイナ受付」を行った場合、薬局は処方データを自動的に取得できます。それ以外の場合でも、処方箋発行時に受け取ったQRコードを読み取るか、引き換え番号と被保険者番号などを提示することで、薬局はデータを取得することが可能です。
これにより、薬局は患者様の到着前に調剤を開始できるケースもあり、薬局での待ち時間が大幅に短縮することが期待されています。とくに忙しい方や体調の優れない患者さまにとっては大きな負担軽減となるでしょう。
また、電子データ管理により処方箋の紛失リスクがなくなることも大きなメリットです。
手書き処方箋で発生していた判読ミスや転記ミスが解消され、調剤の安全性が向上することに加えて、薬局では事前に処方内容を確認できるため、在庫確認や疑義照会をスムーズに行えるようになり、業務の効率化が図られます。
また、処方箋のデジタル管理により紙の保管スペースや管理コストが削減されるほか、HPKIカードを用いた調剤結果登録が義務化されることで、データの信頼性が確保されます。
患者さまの薬歴情報をリアルタイムで参照できるため、重複投薬や相互作用の確認が容易です。
また、患者さま自身も過去の薬剤情報の提供に同意することで、マイナポータルで過去5年分の服薬情報を確認できるため、健康管理に役立てることができます。
上記のことから、電子処方箋に未対応の薬局は、早急にシステムの導入やスタッフの教育を進める必要があるのです。
特定薬剤管理指導加算3-ロの見直し
2025年4月からは、特定薬剤管理指導加算3-ロの点数が5点から10点に引き上げられました。
この加算は、2024年10月に導入された長期収載品の選定療養制度や医薬品供給不安定の影響により、調剤前に医薬品の選択に関する情報提供や指導が必要な患者さまに対して算定されます。
《点数引き上げの背景》
後発医薬品との差額を患者さまに自己負担いただく選定療養制度では、初回調剤時の丁寧な説明が必須となり、業務負荷が増大しています。
2024年11月時点で供給停止や限定出荷の品目が多数発生しており、異なる銘柄への変更時にも新たな説明が必要となるケースが増加しています。
-
▼参考資料はコチラ
医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し|厚生労働省
電子処方箋の現況と令和7年度の対応|厚生労働省
電子処方箋の進捗状況について|厚生労働省
中間年改定の年に行う期中の診療報酬改定について|厚生労働省
2025年4月期中改定を受けて薬剤師が注力すべきこと

医療DXのさらなる推進と薬学的管理の質向上が評価される今回の改定において、薬剤師が注力すべきことをご紹介します。
患者さまへのわかりやすい説明の徹底
今回の改定では、マイナ保険証の利用促進や電子処方箋の本格運用、特定薬剤管理指導加算3-ロの見直しなど、患者さまに直接関わる内容が多く含まれているため、これらの変更点について患者さまにわかりやすく説明することが重要です。
マイナ保険証の利用促進では「過去のお薬の情報がすぐに確認できる」「重複投薬や相互作用のチェックがより確実になる」といった具体的なメリットを丁寧に説明しましょう。とくに高齢の患者さまには、カードリーダーの使い方を実際に見せながら案内し、不安を和らげる配慮が大切です。
電子処方箋については「処方箋の紛失リスクがなくなる」「薬局での待ち時間が短縮される可能性がある」「マイナポータルで自分の服薬情報を確認できるようになる」など、患者さまにとってのメリットを中心に説明することで理解を得やすくなります。
とくに、初めて電子処方箋を利用する患者さまには、従来の紙の処方箋との違いや新しい受付の流れについて丁寧に説明することを心がけましょう。
また、長期収載品の選定療養や医薬品の供給不足に関連する説明(特定薬剤管理指導加算3-ロ)においては、患者さまが混乱しないようにわかりやすい言葉で状況を伝えることが重要です。自己負担額の変更が生じる場合は、具体的な金額を示しながら説明することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
さらに、待合室にはポスターやリーフレットを設置し、来局前から情報提供を行うことも効果的です。
これらの説明ツールは、できるだけ専門用語を避け、図や表を使って視覚的にわかりやすく作成しましょう。
薬局側のしっかりとした整備
今回の診療報酬改定に対応するためには、薬局側の体制整備も欠かせません。とくにシステム面と業務フローの両面からの準備が必要となります。
マイナ保険証の利用率向上には、カードリーダーを受付カウンターの見やすい場所に設置し、「マイナンバーカードをかざしてください」と案内表示を明確にしましょう。
利用率は定期的に確認し、目標達成状況を分析して対策を検討します。
電子処方箋対応には、対応可能な薬歴システムやレセコンの導入・更新が必要です。紙処方箋との混在を想定した業務フローを整備しスタッフ全員に教育を行いましょう。
また、特定薬剤管理指導加算3-ロの算定強化に向けては、長期収載品のリストや差額計算方法についての情報を整理し、すぐに参照できるようにしておくことが効率的です。
セキュリティ対策
医療DXの推進に伴い、薬局でも情報セキュリティ対策の重要性がますます高まっています。
厚生労働省のガイドラインでは、患者さまの大切な情報を守るために、薬局内でのアクセス権限の管理やアカウントの適切な運用、パスワードや認証方法の見直し、データのバックアップ体制の整備などが推奨されています。
薬剤師としては、日々の業務の中で「誰がどの情報にアクセスできるか」を意識し、不要なアカウントが残っていないか定期的に確認しましょう。
また、パスワードは他人に教えず、推測されにくいものを設定することが大切です。システムの障害や情報漏洩など万が一のトラブルが発生した場合の対応手順も、事前にスタッフ間で共有しておくと安心です。
さらに、職員全員で定期的にセキュリティ研修を受け、最新の注意点や脅威について理解を深めましょう。退職者が出た場合には、速やかにアカウントの削除や権限の見直しを行うことも忘れずに。
こうした日々の積み重ねが、患者さまの信頼につながります。
診療報酬改定を踏まえて今後の薬局経営について考えよう
2024年度診療報酬改定は、医療DXの推進や地域在宅医療への貢献を重視し、薬局経営に大きな変化をもたらしました。マイナ保険証や電子処方箋の活用、生活習慣病管理料の再編、後発医薬品使用促進など、薬局に求められる役割はさらに広がっています。
今後はこれらの変化に柔軟に対応し、システム導入などの初期投資を前向きに検討することで、業務効率化や新たな収益機会の創出につなげることが重要です。
「患者さま本位の薬局づくり」を意識し、地域医療に貢献できる体制を整えていきましょう。
ファルマラボ編集部
「業界ニュース」「薬剤師QUIZ」 「全国の薬局紹介」 「転職成功のノウハウ」「薬剤師あるあるマンガ」「管理栄養士監修レシピ」など多様な情報を発信することで、薬剤師・薬学生を応援しております。ぜひ、定期的にチェックして、情報収集にお役立てください。
あわせて読まれている記事
\登録無料!簡単約1分/
ファルマラボ会員特典
- 薬剤師の業務に役立つ資料や動画が見放題!
- 会員限定セミナーへの参加
- 資料・セミナー・コラムなど最新リリース情報をお知らせ