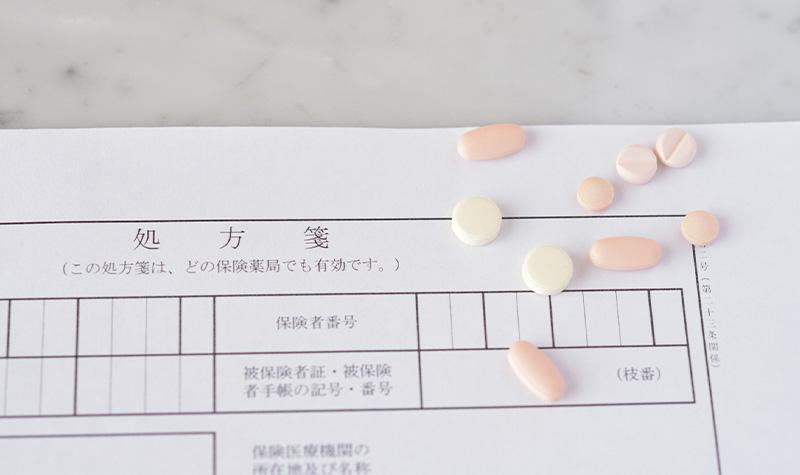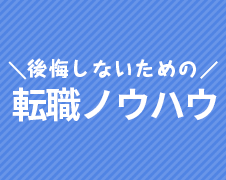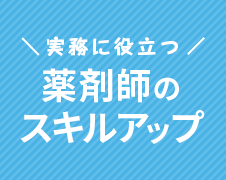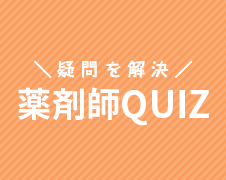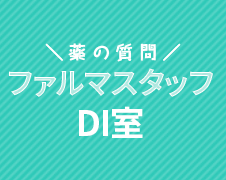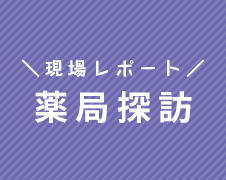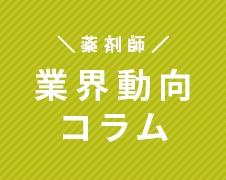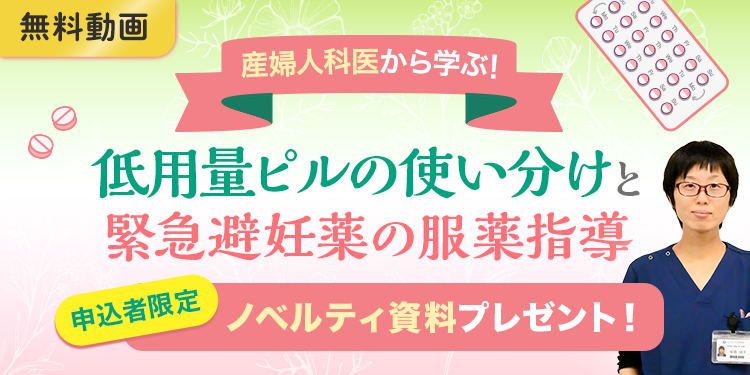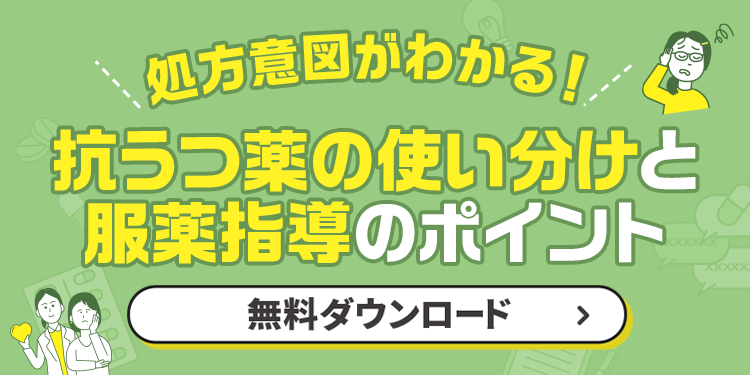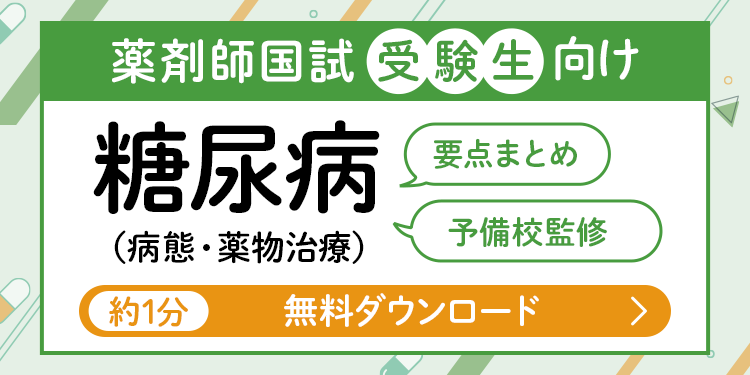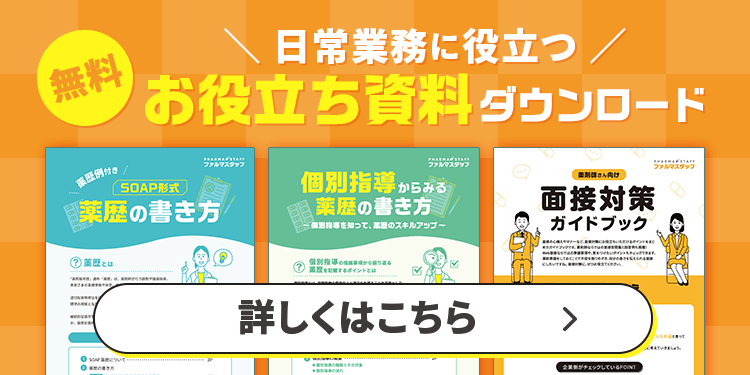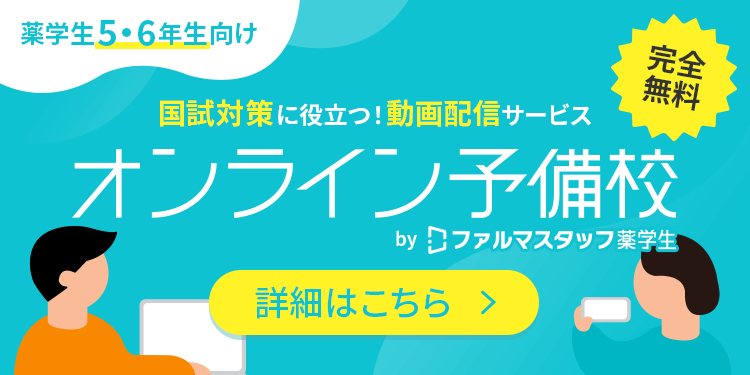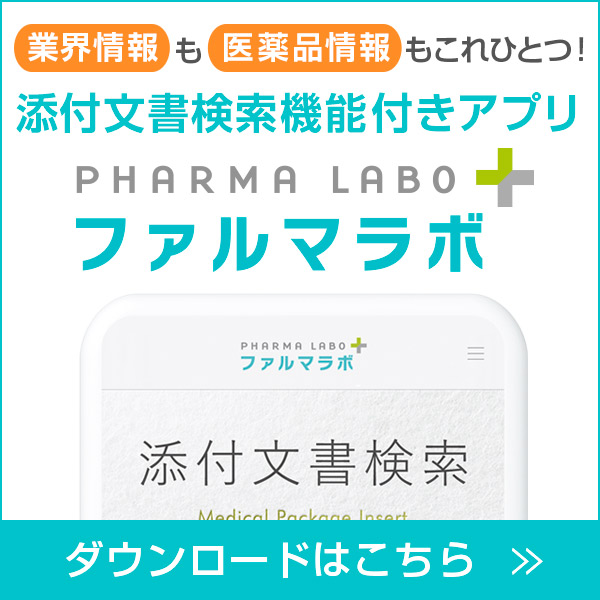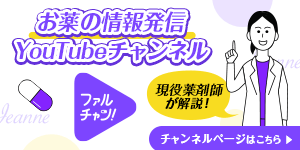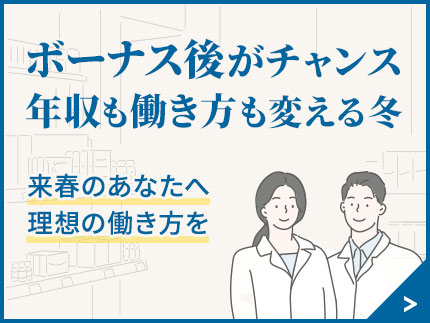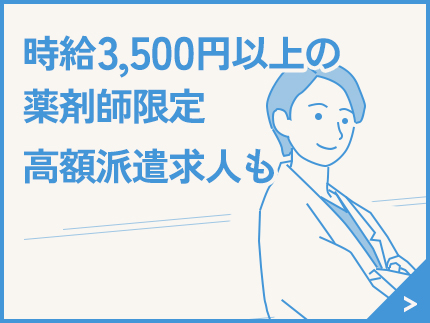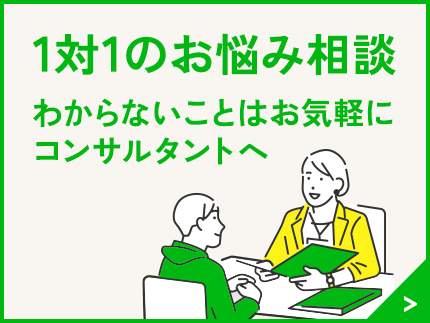- 公開日:2018.08.22
- 更新日:2025-04-22
薬剤師が知っておきたい!「服薬指導」5つのポイントと会話例

患者さまに適切な薬物治療を提供するために欠かせない服薬指導。
しかし、患者さま一人ひとりの状態を把握し、薬剤の知識を踏まえた上で適切なコミュニケーションを取ることは、とくに経験の浅い薬剤師にとって大きな課題となっています。
本記事では、服薬指導の基本から実践的なコツ、具体的な会話例まで、現場ですぐに生かせる情報をご紹介します。
新人薬剤師の方はもちろん、さらなるスキルアップを目指すベテラン薬剤師の方もぜひ参考にしてみてください。
- 服薬指導の基本と重要性
- 服薬指導の際、患者さまに説明すべきポイントは?
- 先輩薬剤師が教える服薬指導のコツ5選!
- 服薬指導時における会話例
- 服薬指導後のSOAP(ソープ)薬歴の書き方
- 服薬指導のコツをつかんで有益な情報提供を目指そう
服薬指導の基本と重要性
患者さまの薬物治療を支える服薬指導は、薬剤師業務の中でも最も重要な役割の一つとなっています。とくに近年は、医薬分業の進展と高齢化社会の到来により、きめ細やかな服薬指導の重要性が一層高まっています。
服薬指導は、薬剤師が患者さまに対して処方された薬の正しい使用方法や注意点を説明し、理解を深めてもらう重要な業務です。薬剤師法に基づく法的な義務であり、厚生労働省が定める「対物業務から対人業務へ」という方向性のもと、その重要性が強調されています。
また、薬剤師の対人業務化に伴い、服薬指導の質がより一層問われるようになっています。とくに、複雑な処方や多剤併用されている患者さまへの丁寧な説明と継続的なフォローアップが欠かせません。
さらに、高齢の患者さまや複数の疾患をお持ちの方には、きめ細かな指導が求められます。
-
▼参考資料はコチラ
厚生労働省『患者のための薬局ビジョン』(平成27年10月23日公表)
服薬指導の流れ
服薬指導には基本となる一連の流れがあります。まず患者さまへのお声がけから始まり、症状や服薬状況の聞き取り、医薬品の説明、質問事項の確認、そしてクロージングという流れで進めていきます。
この基本的な流れを押さえた上で、患者さまの年齢や疾病、体調、既往歴、併用薬などに応じて、重視するポイントを変えていくことが大切です。
また、令和2年9月より、調剤時に加えて調剤後の継続的な服薬指導・服薬状況等の把握も義務として規定されています。
▼関連記事はコチラ
服薬指導の流れとポイントを徹底解説。先輩薬剤師が答える【お悩みQ-A】
▼参考資料はコチラ
対人業務の充実|厚生労働省
服薬指導の際、患者さまに説明すべきポイントは?

服薬指導では、患者さまに必要な情報を漏れなく伝える必要があります。
しかし、ただ情報を伝えるだけでは十分ではありません。
患者さまの理解度や生活環境に合わせて、適切な説明を行うことが重要です。
基本的なポイント
まずは以下の基本的な項目について、患者さまの理解度に合わせて説明していきましょう。
薬の名称と効能・効果を分かりやすく説明します。とくに、初めて処方される薬については丁寧な説明を心がけましょう。
服用のタイミングや1回量など、具体的な服用方法を説明します。また、患者さまの生活リズムに合わせた服用タイミングの提案も大切です。
食事の影響を受けやすい薬かどうかや、健康食品や市販薬との相互作用について説明します。
また、生活上の注意点として、アルコールとの関係や自動車運転への影響などについても具体的に説明しましょう。
温度や湿度、光による影響を考慮した適切な保管方法を説明します。とくに夏場の保管や、小さなお子さまの手の届かない場所での保管などについても触れましょう。
処方薬ごとの重要な説明ポイント
薬の特性によって、重点的に説明すべきポイントが異なります。
そのため、薬剤の特徴を踏まえた上で、以下のような点に注意して説明を行います。
副作用の初期症状と対応方法を具体的に説明することが重要です。とくに、いつもと様子が違う場合の対処法や、すぐに受診が必要な症状について明確に伝えましょう。
治療効果を最大限に引き出すために、なぜ継続服用が重要なのかを分かりやすく説明します。また、自己判断での中止を防ぐため、治療の意義についても丁寧に説明しましょう。
服薬だけでなく、食事や運動などの生活習慣改善の重要性も併せて説明します。
継続的な服薬をサポートするポイント
服薬アドヒアランスの向上のため、以下の点についても丁寧な説明が必要です。
薬の特性に応じた適切な対応方法を説明します。次の服用時間までの間隔や、絶対に避けるべき対応についても具体的に伝えましょう。
予測される副作用とその初期症状、対処方法について説明します。とくに重大な副作用については、早期発見・早期対応の重要性を強調しましょう。
適切な服薬管理のため、残薬の確認方法や保管方法を説明します。必要に応じて一包化や服薬カレンダーの活用も提案しましょう。
継続的なフォローアップの重要性を説明し、定期的な受診や来局を促します。気になることがあればいつでも相談できることも伝えましょう。
先輩薬剤師が教える服薬指導のコツ5選!

ここで、長年経験のある薬剤師が教える、服薬指導のコツをご紹介します。
コツ① 一方的に話をせず、患者さまの話を聞く
新人薬剤師によくある服薬指導として、薬の説明を"一方的に"してしまうことが挙げられます。薬の情報を伝えたいという姿勢は素晴らしいですが、コミュニケーションが一方的になってしまうのは望ましくありません。
しっかりと患者さまの話を聞き、それに応答する形で服薬指導をすすめましょう。
重要なのは「対話」を意識することです。
コツ② 「気づき・気配り」で患者さまに寄り添う
薬剤師にとって大切なのは、「相手の立場に立ってものを考えること」です。たとえば、足の不自由な患者さまには席で話し、耳の遠い患者さまには声を大きくして話すなど、状況に応じて対応します。
また、薬袋の文字を指し示しながら説明するなど、患者さまの立場に立つことで、伝わりやすい方法が見えてきます。
さらに、待合室での気配りも大切です。小さいお子さまを連れた保護者に対する配慮や、何かを探している方へのお声がけなど、積極的に周囲に気を配ることで、患者さまに寄り添った服薬指導ができるようになるでしょう。
コツ③ 服薬指導の長さは、臨機応変に
患者さまの状況によって、服薬指導にかける時間は柔軟に調整する必要があります。薬の服用方法で悩みを抱えている患者さまに対して簡潔すぎる服薬指導をしてしまうと、不安な気持ちにさせてしまいます。
一方で、急いでいる患者さまや、待ち時間が長くイライラしている患者さまに対して丁寧すぎる服薬指導をしてしまうと、クレームの原因となることも。伝えるべき内容は確実に伝えつつ、状況に応じて説明の濃淡をつけることが大切です。
コツ④ 一度の服薬指導で完結する必要はない
新人薬剤師のうちは、すべての情報を一度に伝えようとしがちです。しかし、患者さまの中には高齢の方も多く、一度ですべてを理解してもらうのは難しい場合があります。
「いろいろ聞いたけれど結局よくわからない」と思われてしまっては、服薬指導の意味がありません。
まずは重要な点に絞って説明し、次回来局時に前回の復習をしながら新しい情報を加えていく、というステップを踏むことで、患者さまの理解度も高まります。
コツ⑤ 指導箋など使えるものはしっかり活用する
服薬指導は、すべてを口頭で済ませる必要はありません。メーカーが作成している指導箋や、自作の説明資料なども積極的に活用しましょう。
たとえば、食前に服用する薬であれば薬袋に大きく「食前」と記載したり、薬剤情報提供書に重要な箇所を蛍光ペンでマークしたりするのもいいでしょう。患者さまが後から見返してもすぐにわかるような工夫を心がけることで、服薬指導の効果は大きく高まります。
服薬指導時における会話例

実際の服薬指導では、患者さまの状況に応じて適切なコミュニケーションを取ることが重要です。ここでは、よくある服薬指導の場面での具体的な会話例とそのポイントをご紹介します。
初回来局時の服薬指導例
薬剤師
「今回処方された高血圧のお薬は初めて服用されますか?」
患者さま
「はい、初めてです」
薬剤師
「では、お薬の効果と飲み方について詳しくご説明させていただきます。普段のお仕事や生活リズムを教えていただけますか?」
患者さま
「朝9時から夕方6時まで事務の仕事をしています」
薬剤師
「わかりました。では、このお薬は1日1回、朝食後に1錠を水またはぬるま湯で服用してください。服用後は降圧作用によって、めまいや立ちくらみを感じることがあるかもしれないので、急に立ち上がらないよう注意し、めまいを感じた際は無理をせず安全な場所で休んでくださいね」・・・
【ポイント】
初回は基本情報の収集が重要です。既往歴やアレルギーの有無などの情報の他、日常生活のリズムや食事の内容、薬を管理する環境などについても確認しましょう。
生活背景を把握することで、より適切な服薬指導の実施が可能です。
ハイリスク薬の服薬指導例
ワーファリン錠を服用中の患者さま
薬剤師
「お薬を服用されていて、鼻血や歯茎からの出血はありませんか?」
患者
「実は最近、歯磨きのときに歯茎から血が出やすくなったような...」
薬剤師
「ワーファリン服用時は歯茎から出血する可能性があります。そのため、歯ブラシを柔らかいものに変更し、あまり強く磨かないようにしてください。大きな出血や血尿、黒色便が見られた場合はすぐに医師に相談してくださいね。また、服用中に納豆やクロレラなどのビタミンKを多く含む食品はとらないよう注意してください」
【ポイント】
ハイリスク薬の場合は、副作用のモニタリングと副作用発生時の対応方法を具体的に説明することが重要です。
患者さま一人ひとりの状況に合わせ、年齢、病状、併用薬などを確認した上で、適切な服薬指導を行いましょう。
アドヒアランス不良時の服薬指導例
薬剤師
「お薬の飲み忘れはありませんか?」
患者さま
「朝と夜は問題ないのですが、昼の分をよく忘れてしまって...」
薬剤師
「職場ではお薬を持ち歩いていないのですか?」
患者さま
「持って行くのを忘れることが多いです」
薬剤師
「では、このような1日分ずつ仕切られたお薬ケースはいかがでしょう?朝、通勤カバンに入れておくだけで済みますよ。スマートフォンのアラームと組み合わせると、より効果的です」
【ポイント】
服薬アドヒアランス向上のためには、患者さまの生活パターンに合わせた具体的な提案が効果的です。一包化や服薬カレンダーなど、さまざまなツールを活用しましょう。
多職種連携における服薬指導例
薬剤師
「訪問看護師から、最近めまいが強くなっていると伺いましたが、どのような状況で起こりますか?」
患者さま
「朝の薬を飲んだ後によくめまいを感じます」
薬剤師
「血圧の記録も低めですね。主治医に状況を報告し、お薬の調整を相談してみます。次回の訪問看護の際に、血圧の様子を特に注意深く見ていただくようお伝えしますね」
【ポイント】
多職種との情報共有を密に行い、それぞれの視点を生かした服薬支援を行うことが重要です。
残薬が多い患者さまへの服薬指導例
薬剤師
「先月お渡しした降圧薬は残っていますか?」
患者さま
「そういえば、だいぶ残っているかも...」
薬剤師
「確認させていただいてもよろしいでしょうか?...1週間分以上残っていますね。どのような時に飲み忘れやすいですか?」
患者さま
「朝は忙しくて飲み忘れが多いです。食後すぐに出勤しないといけないので」
薬剤師
「なるほど、朝は時間に追われるのですね。では、朝食前にお薬を1包ずつ出しておく方法はいかがでしょうか?食事の準備と一緒に、コップとお薬を用意しておくと忘れにくいですよ」
【ポイント】
残薬が多い場合は、その原因を丁寧に聞き取り、例えば服薬カレンダーの活用や1包化の提案など、患者さまの生活リズムに合わせた改善策を提案します。
服薬指導後のSOAP(ソープ)薬歴の書き方
SOAP形式での記載が一般的です。
S(Subjective):主観的データ(患者さまが直接訴える情報など)
O(Objective):客観的データ(医療従事者が観察した情報など)
A(Assessment):SやOを基に解釈・分析・判断したこと
P(Plan):SやO、Aを基に導き出した今後の計画の記載
特に重要なのはA(Assessment)の部分です。
患者さまの状態をどのように判断し、どのような指導が必要と考えたのか、その根拠を明確に記載します
【SOAP薬歴の書き方】記入事例から速くわかりやすく書く方法を解説
服薬指導のコツをつかんで有益な情報提供を目指そう
服薬指導は、薬剤師の専門性が最も発揮される重要な業務です。
患者さまの状態を適切に把握し、一人ひとりに合わせた指導を行うことで、医薬品の適正使用と治療効果の向上に貢献できます。
本記事では、基本的な指導のポイントから実践的な会話例まで、現場ですぐに活用できる内容をご紹介しました。日々の業務を通じて、患者さまに信頼される服薬指導を実現していきましょう。
ファルマラボ編集部
「業界ニュース」「薬剤師QUIZ」 「全国の薬局紹介」 「転職成功のノウハウ」「薬剤師あるあるマンガ」「管理栄養士監修レシピ」など多様な情報を発信することで、薬剤師・薬学生を応援しております。ぜひ、定期的にチェックして、情報収集にお役立てください。
あわせて読まれている記事
\登録無料!簡単約1分/
ファルマラボ会員特典
- 薬剤師の業務に役立つ資料や動画が見放題!
- 会員限定セミナーへの参加
- 資料・セミナー・コラムなど最新リリース情報をお知らせ