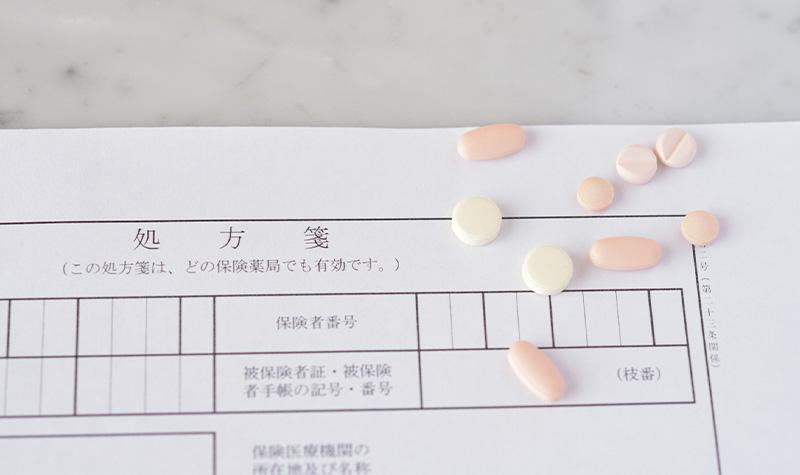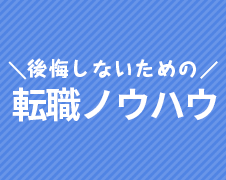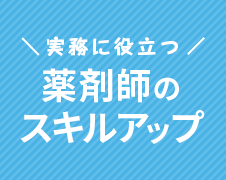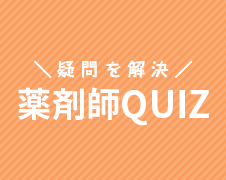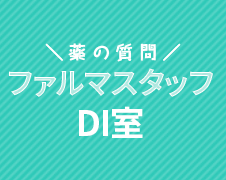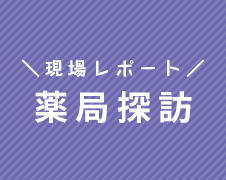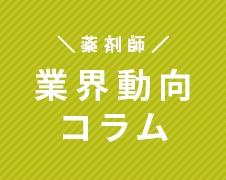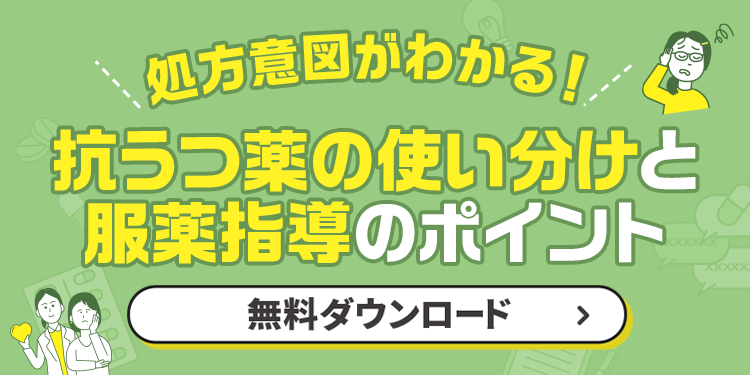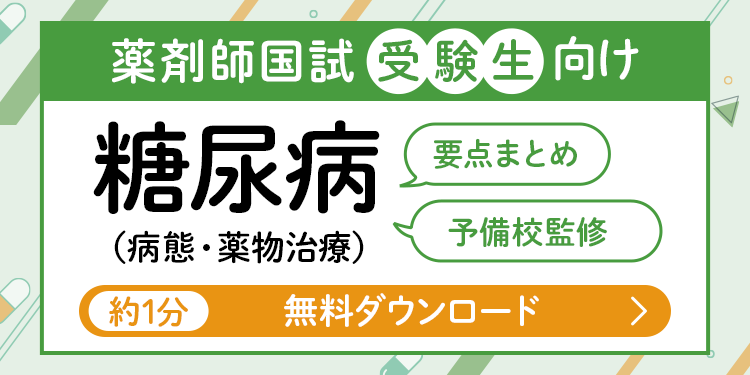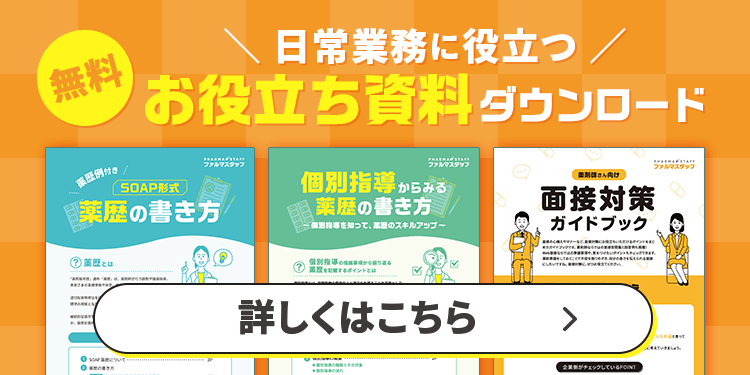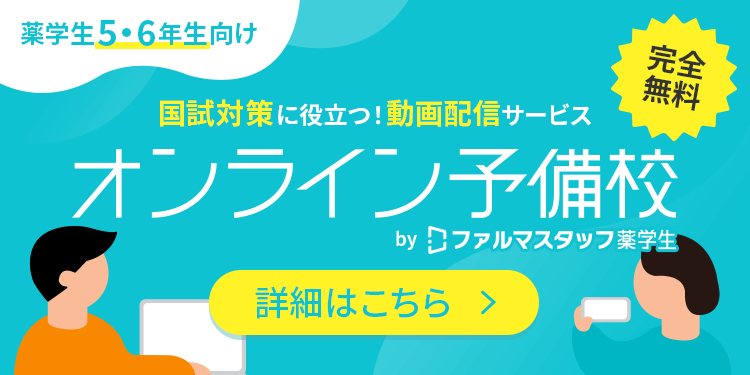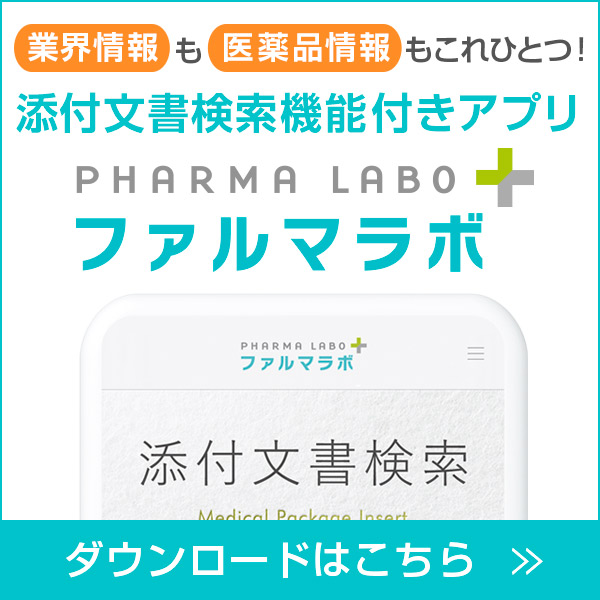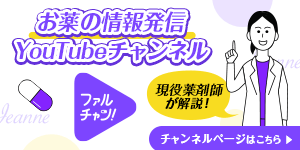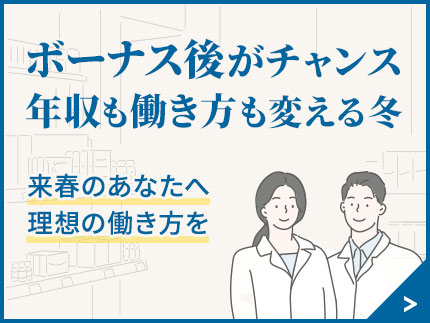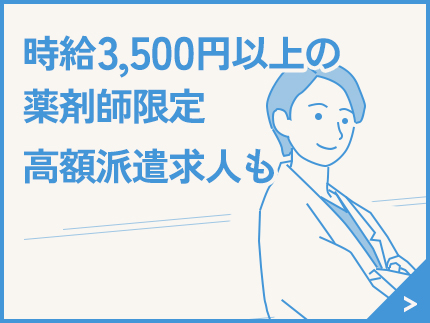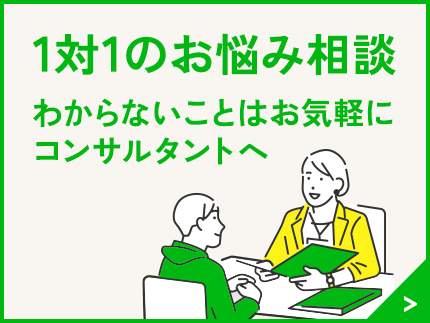- 公開日:2024.05.23
要指導医薬品とは?成分の一覧や効能効果を解説

OTC医薬品を販売する際、患者さまから薬の説明に関する相談を受けたことがある薬剤師は多いと思います。とくに、要指導医薬品を販売する場合には、薬剤師による対面での情報提供や指導が法律で義務付けられています。
この記事では、要指導医薬品の定義や品目と効果の一覧表などを解説していきます。また、今注目されている、内臓脂肪減少薬「オルリスタット」についても言及しているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
要指導医薬品とは?
薬局やドラッグストアに並んでいるOTC医薬品の中でも、要指導医薬品は薬剤師による対面でのみ販売が可能です。ここでは、要指導医薬品の定義や重要性、他のOTC医薬品(一般用医薬品)との違いを解説していきます。
要指導医薬品の定義
要指導医薬品は、処方せんなしで購入できるOTC医薬品の一つです。販売や購入にあたっては、薬剤師による対面での情報提供が法律により義務付けられており、インターネット販売は許可されていません。要指導医薬品に指定される薬は、以下の3つのカテゴリーに分類されます。
要指導医薬品は購入者が適切に薬を使用できるよう、医療用医薬品と一般用医薬品の間に設けられた区分です。
要指導医薬品の重要性
要指導医薬品は、OTC医薬品としての安全性に関するデータが限られており、その取扱いには十分な注意が必要です。安全性に配慮するため、要指導医薬品を購入する際には、必ず薬剤師から対面での指導や情報提供を受けることが義務付けられています。なお、要指導医薬品は、販売開始から原則3年後に一般用医薬品へ移行されます。
セルフメディケーションについて深く知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
【具体例つき】セルフメディケーションの時代、薬剤師の仕事や役割はどうかわる?
要指導医薬品と一般用医薬品の違い
OTC医薬品には要指導医薬品と一般用医薬品があり、その違いは、以下の表のとおりです。
| 要指導医薬品 | その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。 | |
| 一般用医薬品 | 第1類医薬品 | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して薬事・食品衛生審議会の意見を聴いた医薬品であって、承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 |
| 第2類医薬品 | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって、厚生労働大臣が指定するもの。 | |
| 第3類医薬品 | 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。 | |
引用:要指導医薬品、一般用医薬品販売の手引き|公益社団法人 日本薬剤師会
要指導医薬品は、アレルギー治療薬や鎮痛剤、かぜ薬など、私たちの生活に身近な薬が多く含まれています。しかし、一般用医薬品よりも副作用のリスクに注意が必要なため、その購入にあたっては、薬剤師による対面での説明が義務付けられています。
一方で、一般用医薬品は比較的副作用のリスクが低く、長年にわたりOTC医薬品として使われてきた実績もあるため、インターネットでの購入が可能です。
このように、副作用のリスクに応じて要指導医薬品と一般用医薬品が区分わけされているのです。次の段落では、要指導医薬品を薬効分類別に紹介していきます。
要指導医薬品の一覧表

厚生労働省が公開している要指導医薬品の一覧を参考に、再審査または製造販売後調査期間中の医薬品と劇薬にあたる医薬品の表を以下に示します(令和6年4月1日時点の情報)。
調査期間中または再審査中の医薬品の一覧
スイッチ直後OTCなど11品目が該当します。
| 成分名 | 薬効分類等 |
| フルルビプロフェン | 消炎鎮痛薬 |
| ロキソプロフェンナトリウム水和物/メキタジン/L‐カルボシステイン/チぺピジンヒベンズ酸塩 | かぜ薬 |
| ロキソプロフェンナトリウム水和物/d-クロルフェニラミンマレイン酸塩/ジヒドロコデインリン酸塩/dl-メチルエフェドリン塩酸塩/グアイフェネシン/無水カフェイン | かぜ薬 |
| ロキソプロフェンナトリウム水和物/ブロムヘキシン塩酸塩/クレマスチンフマル酸塩/ジヒドロコデインリン酸塩/dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | かぜ薬 |
| フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸プソイドエフェドリン | 耳鼻用内服薬 |
| オキシコナゾール硝酸塩 | 膣カンジダ用薬 |
| オルリスタット | 内臓脂肪減少薬 |
| ポリカルボフィルカルシウム | 過敏性腸症候群治療薬 |
| ヨウ素/ポリビニルアルコール(部分けん化物) | 点眼薬 |
| イトプリド塩酸塩 | 胃腸薬 |
| ナプロキセン | 解熱鎮痛薬 |
| セイヨウハッカ油 | 過敏性腸症候群治療薬 |
| プロピベリン塩酸塩 | 過活動膀胱治療薬 |
| オキシメタゾリン塩酸塩/クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 鼻炎用点鼻薬 |
| セイヨウトチノキ種子エキス | 下肢のむくみ改善薬 |
劇薬にあたる医薬品の一覧
ホルマリンは販売中止のため、3品目が該当します。
| 成分名 | 薬効分類等 |
| ヨヒンビン塩酸塩 | 勃起障害等改善薬 |
| ヨヒンビン塩酸塩/ストリキニーネ硝酸塩/パントテン酸カルシウム/ハンピ末 | 勃起障害等改善薬 |
| 塩酸ヨヒンビン/ガラナエキス/ハンピ末 | 勃起障害等改善薬 |
| ホルマリン ※平成26年3月販売中止 | 殺菌消毒薬 |
要指導医薬品の成分で注目されているオルリスタットとは?

脂肪の吸収率を下げる働きのあるオルリスタットについて以下の内容を解説していきます。
具体的に見ていきましょう。
オルリスタットの作用機序と効果
オルリスタットは消化管内のリパーゼの働きを阻害して、脂肪の吸収率を低下させる薬です。食事から摂取した脂肪の吸収を抑制できれば、体重減少にも寄与します。また、オルリスタットを食事療法や運動療法と併用するケースもあります。
オルリスタットの適応となる患者さま
オルリスタットの内服に適応がある人は、以下の2つの条件を満たす場合です。
また、以下に当てはまる方は使用してはいけません。
その他にも、飲み合わせで注意しないといけない薬もあるため、併用薬がある場合はしっかりと確認が必要です。
オルリスタットの服薬指導における注意点
オルリスタットは、あくまでも生活習慣改善の補助的な役割を担っている点を購入時に理解してもらう必要があります。食生活や運動習慣の改善は非常に重要で、薬の使用のみに頼るべきではない旨を伝えましょう。
また、油分の多い食事を摂った場合、おなかが張ったり油っぽい便が出たりするなどの消化器系の副作用があらわれる可能性を説明し、注意を促すことも大切です。
要指導医薬品に関する議論や抱える課題
要指導医薬品に関する懸念や課題について、以下の3つの例をあげて解説していきます。
実際に厚生労働省により論議が行われている課題もあるため、今後の動向が注目されています。
オンライン服薬指導の実施検討
処方薬のオンライン服薬指導が可能になったことを受け、要指導医薬品のオンライン服薬指導も検討され始めました。しかし、本人以外の購入や大量購入などの問題が危惧されており、インターネット販売ではそれらの問題がより顕著になると想定されます。不適切な使用につながる恐れがあるため、現状要指導医薬品のオンライン服薬指導は実現されていません。
要指導医薬品に関する販売規制について、より詳細に知りたい方は以下の記事もご参照ください。
【2023年版】医薬品販売の規制緩和で、薬剤師はどうなる?-課題とこれから-
薬局や店舗の体制不備
取り扱いが少ない劇薬を含めた要指導医薬品に対して、薬剤師の知識が不足しているなど、適正な販売が行えていない実情が課題としてあげられています。薬剤師が十分な知識を習得し、適切に服薬指導を行える体制づくりが必要不可欠です。
濫用(乱用)や誤用の恐れがある医薬品の取り扱い
濫用の恐れがある薬について名前や年齢の確認、他店舗での購入状況の確認などが行われていますが、このような薬剤による急性中毒などの有害事象が発生していることも事実です。便漏れなどの副作用が出やすいオルリスタットは、濫用のリスクが高い薬剤とは言えないかもしれません。しかし、誤った知識による不適切使用には注意が必要です。
要指導医薬品の服薬指導におけるポイント
服薬指導を行う際には、要指導医薬品についてしっかり理解を深めておくことが大切です。最後に、購入者に適切に薬を使用してもらうため、抑えるべきポイントを2つ紹介します。
患者さまへの質問事項を決めておく
薬局や店舗に勤める薬剤師間で、生活習慣や既往歴、併用薬の確認などの質問事項をあらかじめ決めておきましょう。質問事項の確認を怠った事例として、ドライアイの診断を受けた方がヒアレインを購入しようとしたケースがあるため、誤った使用を防ぐためにも販売前の確認が必要です。具体的には確認事項の一覧表を作るなどして、薬剤師による服薬指導の質に差が出ないよう、工夫しましょう。
副作用や使用上の注意をわかりやすく伝える
薬の副作用や使用のポイントを、購入時にわかりやすく伝えることが非常に重要です。また、副作用が現れた場合の対処法や医療機関の受診タイミングを指導することにより、購入者の不安軽減につながります。
要指導医薬品の最新情報を知って正しく服薬指導を実施しよう
要指導医薬品は、購入者の安全を守るために設けられた規制区分です。その役割を十分に果たすためにも、薬剤師一人ひとりが高い意識を持ち、服薬指導にあたる必要があります。
本記事を参考に要指導医薬品についての知識を深め、患者さまの適正使用を促進していきましょう。

監修者:青島 周一(あおしま・しゅういち)さん
2004年城西大学薬学部卒業。保険薬局勤務を経て2012年より医療法人社団徳仁会中野病院(栃木県栃木市)勤務。(特定非営利活動法人アヘッドマップ)共同代表。
主な著書に『OTC医薬品どんなふうに販売したらイイですか?(金芳堂)』『医学論文を読んで活用するための10講義(中外医学社)』『薬の現象学:存在・認識・情動・生活をめぐる薬学との接点(丸善出版)』
あわせて読まれている記事
\登録無料!簡単約1分/
ファルマラボ会員特典
- 薬剤師の業務に役立つ資料や動画が見放題!
- 会員限定セミナーへの参加
- 資料・セミナー・コラムなど最新リリース情報をお知らせ