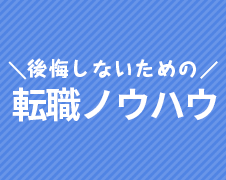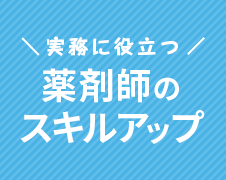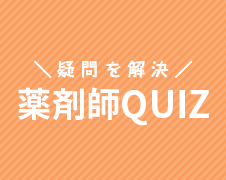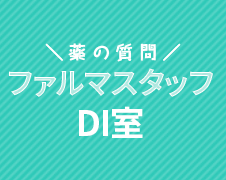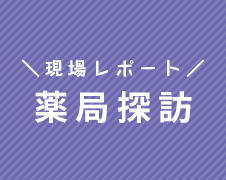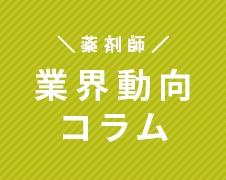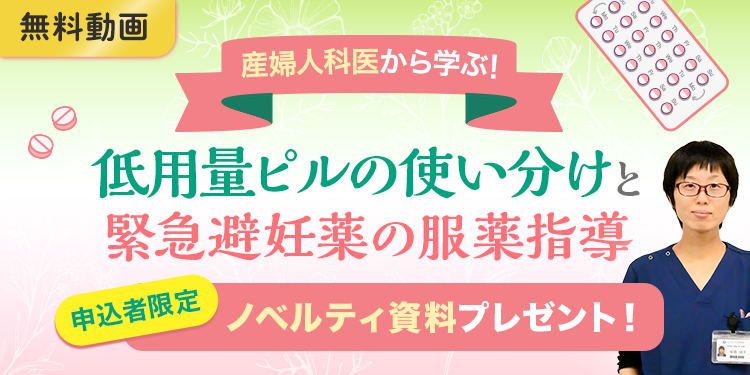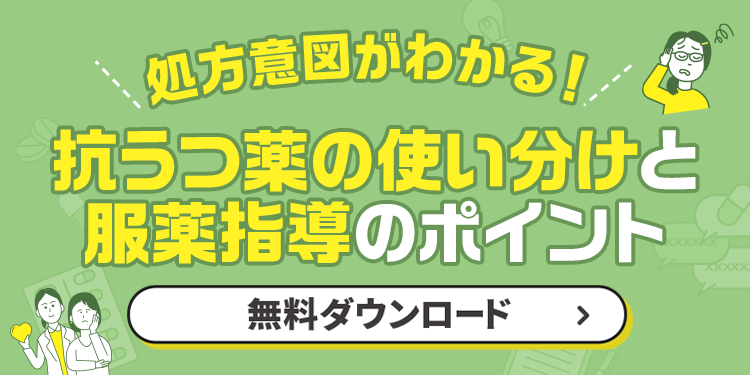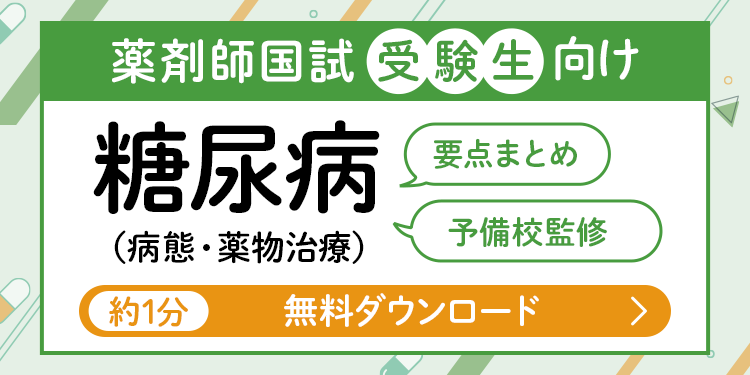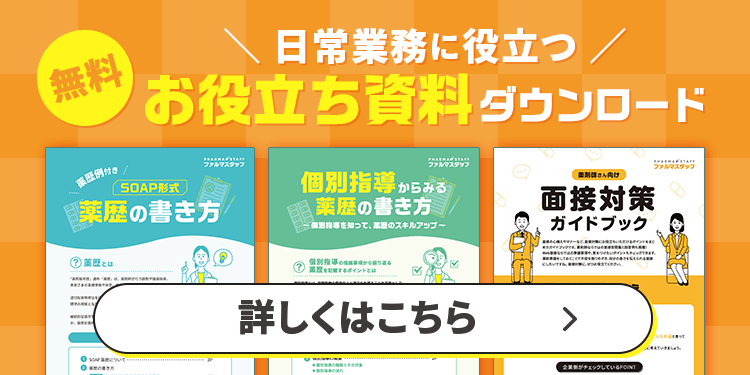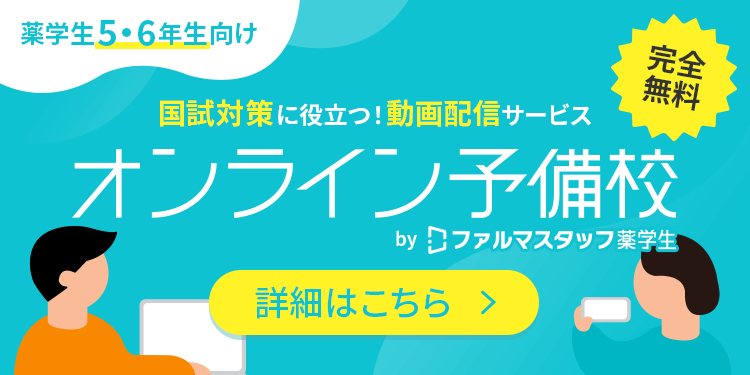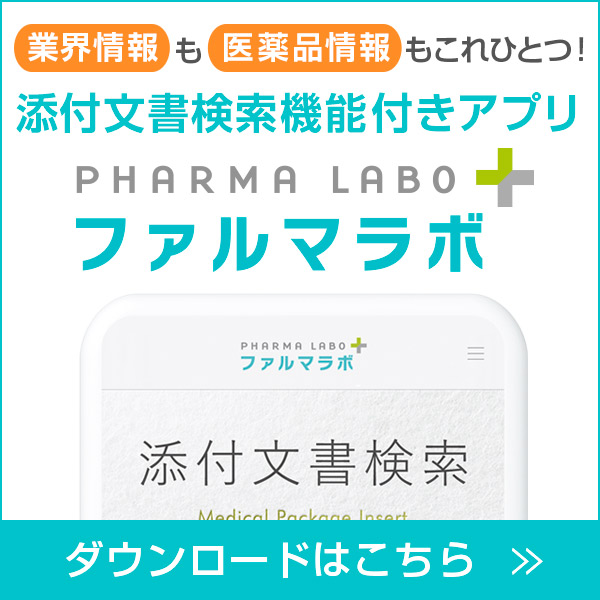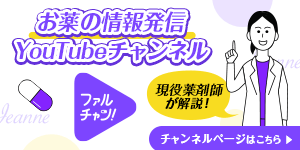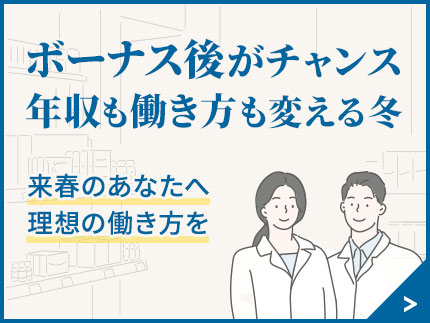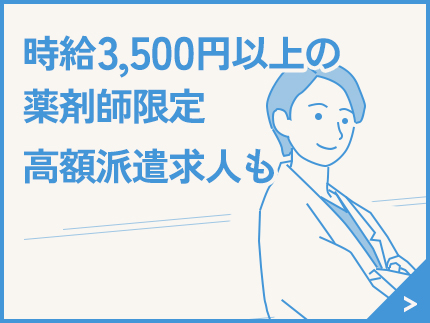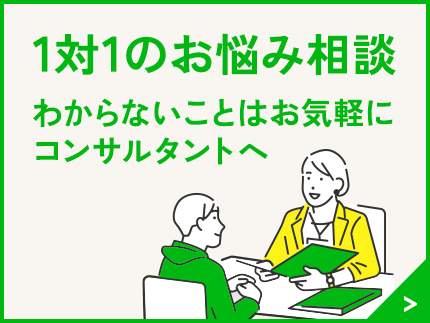|
異型狭心症(冠攣縮性狭心症)とは、冠動脈が一時的に痙攣することで血管内が狭まり、心臓への血流が悪くなる状態を指します。胸が締め付けられる、息が切れるなどの症状が安静時に発現する病気です。 一方で、安定狭心症(労作性狭心症)とは、冠動脈の動脈硬化により血管内が狭まり心臓への血流が悪くなることで、同様の症状が主に運動時に発現する疾患です。 治療薬として、いずれもカルシウム拮抗薬、硝酸薬、ニコランジルといった血管拡張作用がある薬が使われますが、β遮断薬は異型狭心症の患者さまには原則として使いません。 β遮断薬が心拍数や心筋収縮を抑えることで、心筋の酸素需要を低下させるため、安定狭心症には効果を発揮します。 ですが、相対的にα受容体の刺激作用が強く現れることで冠攣縮が引き起こされる恐れがあります。 プロプラノロールは、添付文書に禁忌として記載されているため、異型狭心症の患者さまには投与できません。禁忌欄に記載がない他のβ遮断薬であっても注意が必要です。 ただし、心不全を合併している場合などには、カルシウム拮抗薬などと併用しながら、β遮断薬(カルベジロールまたはビソプロロール)を低用量からはじめ、狭心症の発作に注意しながら投与することがあります。 また、カルテオロール塩酸塩を配合した点眼薬でも冠攣縮が引き起こされることがまれにあるので注意しましょう。 患者さまの狭心症の種類によっては、β遮断薬の処方可否が異なるので慎重に判断する必要があります。 異型狭心症の場合、冠動脈に対する選択性が高いカルシウム拮抗薬であるベニジピンやジルチアゼムが第一選択薬として用いられます。 安定狭心症の場合、動脈硬化の程度に応じて抗血小板薬が使われることが多いです。処方内容から病名を推測できる場合でも、患者さまに直接確認することが重要です。 また、マイナンバーカードに紐づけられた健診情報や診療報酬明細書(レセプト)の既往歴情報も確認してみると良いでしょう。 処方監査・服薬指導のPOINT異型狭心症の患者さまにプロプラノロールが処方された場合は、禁忌となるため、必ず疑義照会を行ってください。 異型狭心症は、他の薬剤との併用状況からだけでは判断が難しい場合があり、注意が必要です。 さらに、狭心症の発作は喫煙や多量の飲酒によって誘発されることがあるため、狭心症の治療をしている患者さまには、喫煙習慣の有無と飲酒量について確認してください。 |
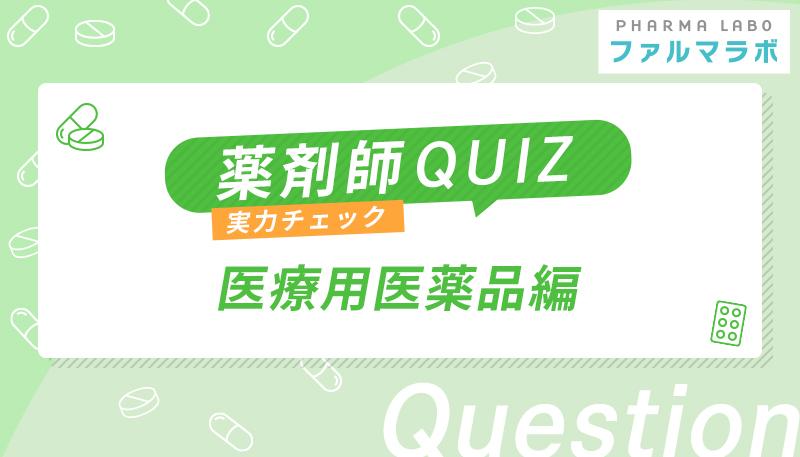
Q |
異型狭心症(冠攣縮性狭心症)の患者さまに禁忌と添付文書に記載されている薬はどれでしょうか? |
掲載日: 2025/04/08
※医薬品情報は掲載日時点の情報となります
※医薬品情報は掲載日時点の情報となります
\登録無料!簡単約1分/
ファルマラボ会員特典
- 薬剤師の業務に役立つ資料や動画が見放題!
- 会員限定セミナーへの参加
- 資料・セミナー・コラムなど最新リリース情報をお知らせ